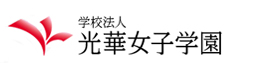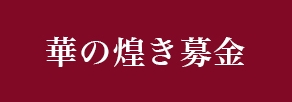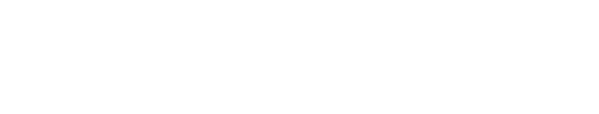光
2026.02.03
本学園の校名「光華」にある「光」という言葉は、仏教において智慧を象徴します。では、その智慧としての光は、私たちの日常のどんな場面で感じられるのでしょうか。
年末、父が命終したことをきっかけに、私はこの問いを改めて見つめ直しました。
父は生前、「宇宙が闇いのは、光が足らぬからではない。光を碍げるものがないから冥いのだ。」という言葉を教えてくれました。浄土はすでにここに満ちているにもかかわらず、その光に生きられない私自身の姿に気づかされます。
さらに父はこうも言いました。
「自家発電の光では人は救われない。」
仏教を深く学び、自力を超えたはたらきの確かさを知っていた父らしい言葉です。
また、父の生き方を思うと、先に浄土へ還られた母の書いた詩がよみがえります。
「私の行方にたちふさがっていた壁が、ナムアミダブツの風に吹かれてパタンとたおれたら、壁のむこうにも広々とした明るい道がありました。」
この詩は、光とは「本当のもの」「本当のこと」に気づかせてくれるはたらきなのだと教えてくれます。
建学の精神に込められた光は、単なる知識ではなく、私たちが本来の姿に気づくための智慧です。その光に照らされながら、教育の場が常に問い直され、磨かれ続けることの大切さを、今あらためて深く心に刻みたいと思います。
なむなむ
2026.01.20
新しい年を迎え、多くの寺院では修正会がお勤めされました。本学園においても、年明けに教職員一同で修正会をお勤めいたします。修正会とは、新たな一年の始まりにあたり、阿弥陀さまの前で身と心を調え、あらためて自らを見つめ直す新年の法要です。
私自身、お寺に生まれ育ちましたので、物心ついた頃から一月一日は、檀家の皆さまと共に修正会をお勤めすることが恒例となっていました。今年も年末に寺へ戻り、修正会の準備をしておりました。
その時に、幼稚園生の姪と甥が来ており、本堂の準備をしていると、二人は当たり前のように阿弥陀さまに向かって「なむなむ」と手を合わせていました。その姿を見て、私はふと、自分は日頃からこのように、純粋な気持ちで阿弥陀さまに手を合わせているだろうかと、問いを与えられたように感じました。
「なむなむ」とは、本当は「南無阿弥陀仏」とのことですが、「阿弥陀仏に帰依します」という意味を持つお念仏です。そして、この「南無阿弥陀仏」こそが、親鸞聖人の教えの中心にあるものです。
『歎異抄』の中にも「本願を信じ、念仏をもうさば仏となる」またと、はっきりと示されています。
私たちはつい、日々の忙しさの中で、形だけになったり、心が置き去りになったりしがちです。しかし、姪や甥の「なむなむ」に触れ、改めて、阿弥陀さまにまかせ、念仏を称えることの大事さを教えられました。みなさんも落ち着いて阿弥陀さんに「なまんだぶ」と称えてみてはいかがでしょうか。
2025年度「成道会」を行いました
2025.12.16
12月8日(月)、釈尊(お釈迦様)が悟りを開かれた日をご縁に、釈尊のみ教えを改めて聞思する機会として、成道会(じょうどうえ)を行いました。
今回の成道会には、光華幼稚園 年長園児と教職員が参列し、真宗宗歌や恩徳讃などの仏教讃歌の斉唱・勤行・焼香などを行いました。

法話では、小椋厚太氏(学園宗教部)がお釈迦様が悟りを開かれるまでのお話を、スライドを使いながら絵本の読み聞かせのように園児にお話されました。


園児も真剣なまなざしでお話を聞き、会の終わりにはしっかりと両手を合わせて合掌しながら恩徳讃を斉唱しました。
義なきを義とすと信知せり
2025.12.10
11月28日は親鸞聖人のご命日ですが、真宗の寺院ではこの時期に、念仏の教えを私たちにお伝えくださった親鸞聖人への報恩感謝と、その教えを聞くご縁の場として報恩講という法要をお勤めします。報恩講では、親鸞聖人が真宗の教えを簡潔にわかりやすくまとめられた正信偈と、仏さまや大切にされている高僧(七高僧)の教えを優しい言葉で皆が一緒に唱えられるようにお作りになった和讃をお勤めします。ちなみに、本学園の式典や宗教行事でよく歌う恩徳讃も報恩講の時にお勤めする和讃にある一文です。
今月のことばは、報恩講の時にお勤めする和讃の中にある「義なきを義とすと信知せり」です。
聖道門のひとはみな 自力の信をむねとして
他力不思議にいりぬれば 義なきを義とすと信知せり (『正像末和讃』第五十四首目)
「自分の力で行を積み悟りをひらこうとする方は、自らをたのみ自分を拠りどころとしているが、阿弥陀如来の不思議なはたらきに帰依すれば、すべては自分のはからい(義)ではなく、阿弥陀如来(他力)のはからいによることなのだと頷くことができますよ」
親鸞聖人はこの「義なきを義とす」ということをお手紙などでも何度も書かれており、とても大切にされています。有名な歎異抄の第十章にも「念仏には無義をもって義とす。不可称不可説不可思議のゆえに」とあり、その著者といわれる唯円も、このことが親鸞聖人の教えの重要な部分であると受け取っておられることを感じることができます。「南無阿弥陀仏という念仏は他力である。それは言い表すことも説明することも想像することもできない、そういうものなのだから」という親鸞聖人の言葉からは、他力をいかに勧めたらよいのかということに苦心された聖人の思いが伝わってきます。
私は最近、親鸞聖人がさまざまなお手紙や書きものに繰り返し「義なきを義とす」という言葉を書かれた意味を、善悪に囚われ善行を積んで良い結果を得ようとする自力の私たち(廃悪修善)に対し、「煩悩から逃れられない凡夫である私たちにはそれこそが難しく、できないことですよ、だからそんな私たちを救うと誓って仏になられたと、経典に書かれている阿弥陀如来のはたらき(他力)、これは言い表すことも説明することも想像することもできないものですが、このお力にお任せするしかないと信じているのです、そして私も法然上人との出会いによってそのことに頷かせていただいたのです」ということをお伝えされたかったのではないかと思うようになってきました。そう思うようになってはじめて真宗大谷派の僧侶であり、大谷大学の初代学長の清沢満之先生が語られた「天命に安んじて人事を尽くす」という言葉を、「ありのままの自分を受け入れ、そんな自分を導いてくださる大きなはからいに任せ最善を尽くそう」という生き方のアドバイスとして受け取ることができるようになりました。これが正しい理解なのかどうかはわかりません。私も親鸞聖人と同様に、さまざまな人との出会いや体験のなかでそのことを確かめていければと思っています。何年か後にまたその報告を「今月のことば」のなかで書ければと思っています。
2025年度 学園報恩講および追悼法要を厳修しました
2025.11.12
11月7日(金)、本学園 光風館講堂において学園報恩講および追悼法要を厳修しました。
学園報恩講は、宗祖親鸞聖人のご命日をご縁に、聖人の恩徳を感謝するとともに、聖人の御教えを改めて聞思する機会として、親鸞聖人によって開顕せられた浄土真宗の教えを建学の精神とする真宗大谷派関係校である本学園において、最も大切にしている宗教行事です。
親鸞聖人のご命日は11月28日ですが、その日は浄土真宗大谷派本山東本願寺で勤められている本山報恩講のご満座(最終日)にあたるため、本学園では、阿部恵水初代中学・高等学校校長のご命日である11月7日に繰り上げて、本学園関係物故者の追悼法要とともに執り行っています。

各校園から、園児・児童・生徒・学生、同窓会代表、学園物故者のご遺族、教職員が参列し、園児から大学生までの代表による献灯、献花、焼香が厳かに行われました。

その後、三因寺 住職の髙田 正城先生をお招きし、法話を行っていただきました。法話をお聞きして、学生たちも親に感謝をすることや、本当の自分になることの大切さを感じたようでした。

この法要は、参加者一人ひとりが亡くなった方々を追悼し、仏教精神について思いを巡らすことで、自分自身を見つめ直す機会となりました。
了義
2025.11.04
仏教とは文字通り「仏の教え」を意味しますが、その教え(教説)の数はどれくらいあるのでしょうか。その多さを形容する言葉として「八万四千の法蘊(はちまんしせんのほううん)」という言葉があり、その教説の内容や長短については形容通り多岐にわたります。また、日本仏教に限りませんが、仏教の宗派(教団)もそれに比例してか数多く存在します。しかしながら、多岐にわたるそれらの教説は、教説間で一見すると矛盾をもつものに見える場合があります。
その典型として挙げられるのが、「一切皆苦」の例です。ある経典(A)では「一切は皆苦である」と説かれる一方で、ある経典(B)では「苦あり、楽あり、中間あり」と説かれます。一見するとどちらかが矛盾しているように見え、仏説が意図するのはどちらなのかという疑問が起こります。
さらに面白い例があります。「諦」という言葉がありますが、現代訳では「真理・真実(Truth)」といったニュアンスで訳されます。有名なものとしては仏教用語の「四聖諦(ししょうたい、四種の聖者の真実)」が挙げられるでしょう。ですが、経典に目を向けてみると、「諦」の数という点では時として様々であり、一貫性がないように思えます。事実、『釈軌論』(しゃっきろん、世親著作)と呼ばれる論書にも諦の数について取り上げている例があります。(詳細については「佛教徒にとってsatyaはいくつあるか」という論文をご参照ください。以下の抜粋も上記論文を参照しました。)
ある経では「聖者の諦は四つである」と説かれ、ある経では「バラモンの諦は三つである」と説かれ、ある経では「諦は二つである。世俗諦と勝義諦とである」と説かれ、ある経では「諦はただ一つである。第二のものはない」と説かれ…(中略)…と説かれるが、こうした性格をもつものが「前後矛盾に対する論難」である。
このように相反する教説を仏教徒はどのように解釈してきたのでしょうか。一方の説だけを仏説として採用し、もう一方を切り捨てたのではありません。一切皆苦の例に戻りますが、AとBという教えがある場合、教説Aを文字通りに解釈し、もう一方Bを文字通りに受け取らず、裏の意味を持つと解釈するという方法を採ってきたのです。この場合、Aの教説を「了義(りょうぎ)」、Bの教説を「未了義」と言います。決して身勝手に解釈していたのではありません。逆もまた然りです。
このような教説の解釈が教相判釈の祖型とも考えられますが、今日、各宗派が数多く存在するのも上述の解釈の歴史があってこそではないでしょうか。(本記事については、「経の文言と宗義―部派佛教から『選択集』へ」という論文を参照いたしました。)
令和7年度 理事長賞表彰を行いました
2025.10.22
10月21日(火)、令和7年度 理事長賞表彰式を行いました。
理事長賞は、本学園の在学生で、学業・文化・スポーツ等において特に優秀な成績を修められた方や、ボランティア活動等で地域に貢献された方を表彰する制度です。
本年度も幼稚園から大学まで多数の推薦が寄せられ、厳正なる選考を行った結果、個人で11名、団体で4団体が選出されました。
阿部理事長から一人一人に賞状と記念品を手渡し、表彰されました。
理事長からは、受賞者の皆さんの活躍が様々なWell-Beingにつながっているという「お祝いの言葉」がありました。
また、受賞者の「お礼の言葉」では、周囲への感謝の気持ちなどが話されました。
受賞者の皆さんのますますのご活躍を期待いたします。




蓮華蔵世界
2025.10.01
ハス(蓮)の学名は「Nelumbo nucifera」(ネルンボ・ヌキフェラ)。ハス科ハス属のインド原産とされる多年性の水生植物です。古来、仏教では睡蓮とともに「蓮華(レンゲ)」と呼ばれ、泥に生え、泥に染まらず、泥の中から美しい花を咲かせることから、清らかな心を象徴するものとして尊ばれてきました。
真宗門徒が親しむ「正信偈」(親鸞聖人が『教行信証』に記された歌)にも「蓮華蔵世界」(『華厳経』)という言葉が見られ、極楽浄土に象徴される調和に満ちた世界を表しています。仏の仰る私たち凡夫も、日常生活の嘘や怒り、嫉み、妬み、欲望、執着という煩悩の濁水の中で、自覚をもち、蓮華のように清々しく生きたいものです。
京都光華高校は、2026年度、通信制課程を新設します。蓮華に因み、校名(愛称)を「RENハイスクール」と名付けました。極楽浄土に咲く蓮華の「青色青光 黄色黄光 赤色赤光 白色白光」(『仏説阿弥陀経』)のごとく、一人ひとりの個性を尊び、大切にし、清らかに光り輝く学校を目指します。ご縁のあった生徒の人生が、在校中も卒業後もWell-Beingなものとなるように、「蓮華蔵世界」の学校創り、共創社会・同朋社会の実現に向けて精進します。
「光華キッズなフェスタ」を開催します
2025.09.24
この度、11月1日(土)に“こどもと「絆」を深める日”をテーマとした地域連携イベント
「光華キッズなフェスタ」を開催します。
当日は、本学園の幼稚園~大学の学びを活かした遊びやブースの他、
子どもたちの健やかな発達に繋がるよう陸上体験やフットボール教室等も実施し、
”ワクワク感みなぎる”一日となるよう準備を進めております。
イベントの詳細はこちらをご覧ください。
小さなお子様(幼児~小学生)が楽しめるイベントとなっておりますので、
ご家族やお知り合いの方をお誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。
私には自分より愛しい者が他に誰もいない
2025.09.05
9月の「今月のことば」は、『相応部経典』に収められている「マッリカー経」からの引用です(中村元『神々との対話I』pp.169-170, 片山一良『相応部』第1巻, pp.313-314)。古代インドに存在したコーサラ国には、パセーナディ王という王がいました。王妃の名はマッリカーといい、夫婦そろって釈尊に帰依し、仏教教団を保護したと伝えられています。
ある日、パセーナディ王とマッリカー妃は高楼に登って語り合っていました。そのとき、王は妃に「そなたには、自分よりもさらに愛しい者が他に誰かいるかね」と尋ねました。王は、妃から「王様、私にとって何よりも愛しいのはあなたです」という答えを引き出し、互いの愛情を確かめ合いたかったのでしょう。古代インドの注釈者も、そのように解釈しています。しかしマッリカー妃は、自分の心に正直に「私には、自分よりさらに愛しい者は、他に誰もおりません」と答えました。そして妃が「王様はいかがですか」と問い返すと、王もまた「私にも、自分よりさらに愛しい者は、他に誰もいない」と率直に答えたといいます。
仏教では、人は誰しも強い自己への執着を抱いていると説かれます。「私が」「私の」と、自分を中心に物事を考えてしまうのです。私たちは自分に執着し、自分の欲望や感情に振り回されながら生きています。「子どものためなら命を捧げられる」と思ったとしても、我が子だからこそそう思えるのかもしれません。そう考えると、マッリカー妃の言葉は、誰もが認めざるを得ない事実を示していると言えるでしょう。人間にとって、自己ほど愛しいものはないのです。
釈尊は、この二人のやり取りを踏まえて、次のように説かれました。「あらゆる方向に、心で探し求めても、自分よりもさらに愛しい者を得ることはない。このように、他の人々にとってもそれぞれの自己は愛おしいものである。それゆえに、自己を愛する者は、他者を害してはならない」。つまり、自分が自分を大切に思うように、他者もまた自分を大切に思っている。そのことに気づき、相手を傷つけずに生きなさいと説かれたのです。
ここで示されているのは、他者への想像力です。自分さえ良ければいいという自己中心的な心に気づき、他者の立場から物事を見ること。これは社会の中で他者と共に生きる私たちに欠かせない姿勢でもあります。人は皆、自分を愛しく思うものですが、その自分本位の見方を少し離れ、他者に寄り添う心を育んでいきたいものです。