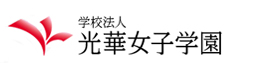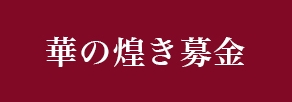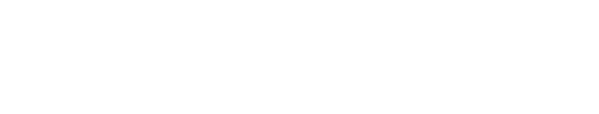光
本学園の校名「光華」にある「光」という言葉は、仏教において智慧を象徴します。では、その智慧としての光は、私たちの日常のどんな場面で感じられるのでしょうか。
年末、父が命終したことをきっかけに、私はこの問いを改めて見つめ直しました。
父は生前、「宇宙が闇いのは、光が足らぬからではない。光を碍げるものがないから冥いのだ。」という言葉を教えてくれました。浄土はすでにここに満ちているにもかかわらず、その光に生きられない私自身の姿に気づかされます。
さらに父はこうも言いました。
「自家発電の光では人は救われない。」
仏教を深く学び、自力を超えたはたらきの確かさを知っていた父らしい言葉です。
また、父の生き方を思うと、先に浄土へ還られた母の書いた詩がよみがえります。
「私の行方にたちふさがっていた壁が、ナムアミダブツの風に吹かれてパタンとたおれたら、壁のむこうにも広々とした明るい道がありました。」
この詩は、光とは「本当のもの」「本当のこと」に気づかせてくれるはたらきなのだと教えてくれます。
建学の精神に込められた光は、単なる知識ではなく、私たちが本来の姿に気づくための智慧です。その光に照らされながら、教育の場が常に問い直され、磨かれ続けることの大切さを、今あらためて深く心に刻みたいと思います。
過去のことば
2025年
12月
11月
10月
4月
3月
2月
1月
2024年
12月
11月
9月
5月
4月
2023年
11月
10月
8月
7月
2月
2022年
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
1月
2021年
11月
10月
9月
8月
7月
3月
2月
2020年
11月
6月
2019年
12月
11月
8月
6月
5月
2018年
11月
9月
8月
5月
4月
3月
2017年
11月
10月
1月
2016年
12月
5月
2015年
11月
9月
1月
2014年
12月
5月
2013年
1月
2012年
2011年
11月
7月
2010年
9月
3月
2009年
12月
11月
8月
3月
2008年
12月
11月
2007年
11月
2006年
12月
11月
10月
2005年
12月
11月
10月
9月
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年