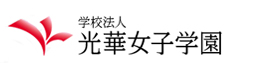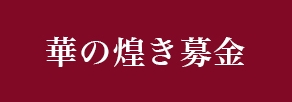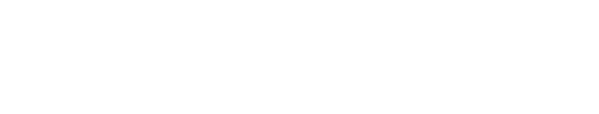2018年度「学園太子忌」を開催しました
2019.02.23
2月22日(金)、本学光風館講堂で学園太子忌を行いました。
学園では、お釈迦様の誕生を祝う「学園花まつり」、宗祖親鸞聖人のご命日に聖人のご遺徳を偲ぶ「学園報恩講」、そして、聖徳太子のご命日に太子のご遺徳を偲ぶとともに、太子が日本にお広めになった仏教の教えを聞思する「学園太子忌」を学園三大行事として営んでいます。

法要では、各校園代表(学生・生徒・児童・園児代表)や教職員が参加し、献灯、献華、勤行に続き、本学園中学校教諭高田正城先生による法話が行われました。
法話では、「共鳴の鳥」のお話や聖徳太子が「十七条憲法」に込められた願いについて紹介され、「すべての命はつながり、関わり合いながら存在しており、皆さんも光華で学んだ自分自身を見つめる目を持ち、他者を思いやり皆で支えあう心を忘れずに、今後も過ごしてください」と結ばれました。

2018年度「涅槃会」を開催しました
2019.02.20
2月15日、本学園 慈光館太子堂にて、釈尊(お釈迦様)入滅の日(=ご命日:2月15日)に、釈尊への報恩の意を表し、み教えを改めて聞思する機会として、涅槃会が行われました。
参加者は在校生を代表して中学1年生と教職員でした。
司会より、本尊の脇に掲げられた大涅槃図を観ながら、お釈迦様が、出家をされ、お悟りを開かれたことや、沙羅双樹のもとで亡くなられた様子についての説明がありました。
音楽法要、勤行に引き続き、藤谷 ゆう学園宗教部員による法話が行われました。
法話では、お釈迦様の弟子の一人である周利槃陀伽のエピソードをお話されました。周利槃陀伽は自分の名前まで忘れてしまうほど物覚えが悪く、周りからも駄目な弟子だと言われ、そんな自分を愚かに感じていましたが、お釈迦様に言われたとおり、「塵を払い、垢を除かん」と称えながら掃除するうちに、「塵と垢」は、教えを聞いて、たくさん知識をつけることが良いことだと思っている自分の執着心であるということに気づきました。
仏教の教えを聞くということは、このように自分を見つめ、自己と向き合っていくことである、とお話され、最後に「涅槃会に参加することで、お釈迦様のみ教えを学び、自分自身を見つめなおす機会としてほしい」と結びました。


「花びらは散っても花は散らない」 金子大栄『意訳歎異抄』
2019.02.01
片付けものをしていたら机の奥から一枚の葉書が出てきた。
「ようやくあたたかくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。私は○○大学に進学が決定し、遅咲きながら桜が咲きました。これからもどうぞよろしくお願いします。○○○○」 目の前にぱっと、明るい笑顔が浮かぶ。九州に生まれた彼女は、幼いときから父親の故郷の京都に憧れていて、中学生の時に祖父母をたよりに京都に来て、本校に入学した。
生徒会や演劇部で活躍した彼女は、まさにバイタリティーのかたまりのようで、その後も活発に京都と九州を往来していた。 訃報が届いたのは、この葉書をもらって間もない頃だったろうか。急な病で、まだ大学在学中のことだった。私は行けなかったが、九州の葬儀には仲間たちが駆けつけたらしい。
二十数年も前の古びた葉書を見つめながら、はたと気づいた。私はこの葉書を数年前にも見て、同じことを思い出していたと。いや一度ではなく、何度も何度も・・・そして、そのたびにまた机の奥に大切にしまっていたことも・・・
彼女に会うことは二度とかなわない。いや、だからこそ私はこの葉書を決して捨てないだろう。そして、また数年後に葉書を見つけ、彼女の記憶を甦らせ、机の奥にそっとしまうのだろう・・・
彼女だけではない。私事で恐縮だが、光華にお世話になって38年、今年最後の一年を終えようとしている私は、ここで多くの「いのち」と出遇い、共に生きてきた。
「ここには君を待っている人がいるんだよ。そのことを忘れてはだめだよ」くじけそうな時に力強く励まして頂いた上司も、「『宗教』の授業を聞いて、私のいのちも意味があるのだと思えるようになりました」難病に苦しみながら、しみとおるような笑顔を私にくれた彼女も・・・今は亡い。
しかし、その笑顔や声は今も鮮やかに私の中に残っている。
「花びらは散っても花は散らない形は滅びても人は死なない」先達の言葉が、今実感を伴って甦る。
みんな生きているのだ。私の中に。そしてつながっていくのだ。大きないのちの源に・・・
「前に生まれん者は後を導き、後に生れん者は前を訪とぶらえ。」(道綽(どうしゃく)禅師『安楽集』より)
「光華」という場で互いに遭い遇う、さまざまな「いのちの願い」が永久に受け伝えられていくことを念じつつ筆を擱く。(宗教部)