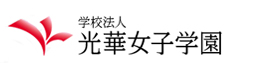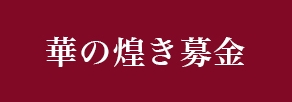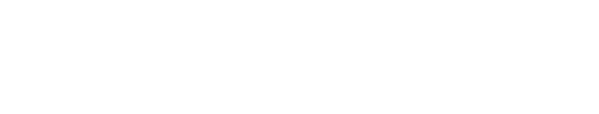一水四見(いっすいしけん)
2019.12.02
さまざまな苦しみや悩みから脱却するためには、正しいものの見方が大切です。しかし、人間は、正しいものの見方をすることはなかなか難しいと思います。学校や会社の中でも、あるいはグループにおいても、一人でも気にいらない人がいると落ち着かないという経験があると思います。しかし、そこには単に「その人」がそこにいるだけです。結局のところ「嫌い」という私自身の心が「あの人さえいなければいいのに」という見方に傾いていき、そこから苦しみが生まれてくるわけです。そうすると、互いに傷つけ合い、最後には苦しみ合う結果になってしまうのです。
「認識の主体が変われば認識の対象も変化する」
仏教の考え方の一つ『唯識』に「一水四見」という言葉があります。一口に水といっても四つの見方に見える。つまり、同じものでも見る立場や心のもちようによって違うように見えてくるという意味です。
① 天人には水がきれいに透き通ってガラスのように見える。
② 人間の私たちには、そのままの水に見える。
③ 魚たちには住み家と見える。
④ 餓鬼には燃えた血膿に見える。
これは「天人」「人間」「魚」「餓鬼」という立場で「水」を見た場合、それぞれ異なって見えることを例えたものです。これを私たちに当てはめてみると、私たち人間は、みんな生まれ育った環境や境遇、受けた教育、経験したことや考えてきたこと、興味を持ったことなどさまざまで、それぞれその人独自の世界観があり、価値観があります。それが大きなひとつの「ものさし」となって、いろいろな事を認識しています。
それでは、自分が見ている世界は、他人から見てどのように見えるのでしょうか。同じものを見ていても、気づかないことがあるのではないでしょうか。
世界というのは、実は同じ一つの世界にみんながいるのではなく、それぞれがそれぞれの世界を作り上げて、それぞれの世界を見ているということです。つまり、人それぞれが各々の世界をもっていて、どこかの接点で互いの世界を共有をしています。そこから「つながり」が生まれてくるわけです。
人生の中で、いろいろな苦しみや悩みに出合った時、ものの見方を私自身が変えることによって、見えなかったものが見えたり、気づかなかったことに気づかされたりして、世界が拓かれていくのだと思います。
2019年度「学園報恩講」を開催しました
2019.11.15
11月7日(木)、本学園(北校地)光風館講堂において学園報恩講を開催しました。
この取り組みは、宗祖親鸞聖人のご命日をご縁に、聖人の恩徳を感謝するとともに、聖人の御教えを改めて聞思する機会として、毎年行っております。
親鸞聖人によって開顕せられた浄土真宗の教えを建学の精神とする真宗大谷派関係校である本学園において、最も大切にしている宗教行事です。
親鸞聖人のご命日は11月28日ですが、その日は本山東本願寺で勤められている本山報恩講のご満座(最終日)にあたるため、本学園では、阿部恵水初代中学・高等学校校長のご命日である11月7日に繰り上げて執り行っています。
また、お亡くなりになられた本学園の卒業生や教職員等、有縁の方々への追悼、法要も併せて執り行いました。
各校園から、園児・児童・生徒・学生、同窓会代表、教職員が参列し、園児から大学生までの代表による献灯、献花、焼香が厳かに行われました。
その後、名和達宣氏(真宗大谷派教学研究所研究員)による法話をお聴きし、自身の考えや思いだけで生きていくのではなく、自然の声や周りの人の声に耳を傾け生きていくことの大切さを考える機会になりました。
期待しない
2019.11.01
皆さんは日々の生活の中で、例えば仕事であれば、「なぜこんなに頑張っているのに認めてくれない?」、「なぜこれくらいのことを部下はわかってくれない?」、私生活であれば、「なぜ夫は私の頑張りに気付いてくれない?」「なぜ妻は自分が仕事に疲れていることに気付いてくれない?」なんて感情を抱いたこと、または口にしたことはないでしょうか?私たちは日々の暮らしの中で、周囲の人に、環境に、過度の期待をしていないでしょうか?他者への過度の期待は、自分自身を息苦しくさせ、目の前で起こっていること(もの)の価値を忘れさせてしまいます。
仏教では、「諸行無常」や「縁起」という言葉でこの世界や私たちの姿をあらわします。この世の全てはとどまることなく常に移り変わっており、原因や条件が相互に関わりあって存在しているという仏教の根本的な考え方であります。そのような中においては、この私も常に変化し続けており、固定した私というものはありません。しかし私たちはこの「ありのままの真実」に気づくことができず、常に自分の欲の赴くままに自分の好き嫌いや、少しでも自分が楽になるように、得するように、などと自己中心的な考え方でのみ物事を捉えてしまっている現状があります。
他者(環境)に対する期待は、「恒常不変な私が存在する」という思い込み、すべてを自己中心的に見てしまう我執(がしゅう)から生じます。我執があることで貪瞋癡(とんじんち)をはじめとする欲望が生まれると仏教は教えます。貪は貪り,瞋は怒り,癡は愚かさや妄想を意味します。例えば,期待をして(貪)応えてもらっても、自分の思いと違えば期待外れとなり不愉快に感じ(瞋)「何もわかってもらえない」(癡)となります。まずはその自己から離れ、相手を認めていくところ、相手を受け入れることが大切であり、そうすることで物事の本質に近づけるのではないでしょうか。
「期待しない」という考え方で日々を過ごしてみると、思うような結果にならなくとも、その原因を自分自身に探し出す習慣がつくのではないでしょうか。少し冷静に、現状を見つめなおして、今身の回りで起こっていることに、当たり前(本当は当たり前ではない日々)と思っていることに、感謝する機会としていただけますと幸いです。(宗教部)
光華女子学園 創立80周年記念スペシャルサイトを公開しました
2019.10.31
2020年9月、光華女子学園は創立80周年を迎え、ワクワクする学園をめざして加速します。
創立80周年の節目を迎えるにあたり、90周年、そして100周年の未来を見据え「光華ビジョン2030」を策定しました。
今後、展開する様々な80周年事業について、スペシャルサイトから発信していきます。
https://gakuen.koka.ac.jp/koka80th/
ぜひご覧ください。
このものたちは私と同じであり,私もこのものたちと同じである 『スッタニパータ』
2019.10.03
「と,世の生きとし生けるものすべてを自分自身だと考えて,それらを殺さず,また殺させないようにしなさい」と続きます。(『スッタニパータ』705偈,榎本文雄ほか『スッタニパータ 釈尊のことば』179頁,中村元『ブッダのことば』153頁)
「多様性」「ダイバーシティ」という言葉をよく耳にします。確かにわたしたちの社会には様々な価値観,人生観,感性を持つ人がおり,それぞれの生き方というものがあります。
多様な価値や生き方を許容し,生活の中で「人それぞれであること」を理解していくことはとても大事なことです。そのため日常の様々な場面で多様性の尊重が謳われています。しかし,社会の中に溢れる「人それぞれ」という言葉に触れるとき,しばしば,他者を受容し共にあろうとする「温かさ」より,決してそれ以上に距離を縮めるつもりがない「よそよそしさ」を感じます。多様性を許容し「人それぞれ」に生きる社会とは,このように個人がバラバラに分断されて生きていくしかない社会なのでしょうか。
仏教説話に,飢えた虎に遭遇した菩薩(ぼさつ,ブッダとなる前の釈尊)の物語があります。この物語を手掛かりに考えてみましょう。
飢えてもう自分の子供さえ食べてしまいそうになっている虎,そこ出くわした人々。Aさんは何か食料がないかを探し,Bさんは虎が死ぬのを待って毛皮をはいで売り飛ばす算段をし,Cさんは見て見ぬふりをし,Dさんは自らの身体を食料として差し出そうとする….この中で「私もこのものたちと同じ」と思うのはどのキャラクターでしょうか。多くの人は,Dさんは無理でもせめてAさんでありたいと思うのではないでしょうか。しかしBさんかもしれない.あるいは,現実的にはCさんのようになってしまう人が大半かもしれません。ところで,この解説を読んでくださった中で,自分はこの虎であると思われた方はおられるでしょうか。
「私」がいま飢えずにいることは,必ずしも「私」の努力によるものではありません。生まれた時代,環境,出会った人々の巡り合わせがいまの「私」にしてくれているのであって,これから先何か大きな出来事があれば,「飢えて子供でさえ食べてしまいそうになる虎」のようになる可能性があります。それほどにわたしたちは「もろい」存在です。しかし,そのもろいわたしを忘れて,わたしたちは,今の自分を当然のものとして,わたしにとっての価値,わたしのモノサシを絶対のものと思ってしまいます。
この経典は,いまの自分に囚われ他者への想像力を失ったわたしが,その自分を振り返り内省し,他者への共感を取り戻す地平を教えてくれています。自分を振り返ることと,他者への共感なくして,多様性というのは成り立たないのかもしれません。(宗教部)
「念仏の衆生を摂取して捨てたまわず」 『仏説観無量寿経』
2019.09.04
標記の言葉は、宗祖親鸞聖人が真実の経典として最も大切にされた浄土三部経のひとつであります『仏説観無量寿経』のなかにある言葉です。「阿弥陀仏の光明が十方世界を照らして、念仏するものを摂め取って決して見捨てない」と説かれています。
宗祖親鸞聖人においては、どのようなものも決して見捨てることのないこの阿弥陀仏の本願念仏の真実の教えを絶え間なく聞思し、進むべき道を正しく照らす生涯の生きる確かな拠りどころとされて人生を生き抜かれました。
経典では、阿弥陀仏を光で表されています。その光を「摂取不捨」というはたらきとして示されています。暗闇を照らす光明は、闇を除き一面を明るくし、安心感を与えてくれます。また、進むべき道、方向をはっきりと示してくれます。そして、最も大切なことは、すべてを同時に誰一人として取り残さずに生きとし生けるものすべてを絶対平等に照らすということです。
それでは、私たちはこの「摂取不捨」というはたらき(光)を具体的に容易に実感できるのでしょうか。源信僧都は『往生要集』のなかで「大悲倦きことなくして常に我が身を照らしたまう」即ち、阿弥陀仏のはたらき(慈悲の光)の中に包まれて生かされているけれども、煩悩の身であるためにそのはたらきをはっきりと見ることも気付くこともできない。そのような煩悩の深い我が身であるからこそ、阿弥陀仏の慈悲がどのようなときでも決して見捨てることなく常に照らし励まし続けてくださっていることがわかる、と記されています。そのように実感するためには自分自身を深く厳しく見つめて、真の自己とはどういう存在なのか、自分の本当の相(すがた)は如何なるものなのかを顕かにすることが最も必要なことです。真の自己がわかれば自ずから私をあらしめてくれている大きな願いがあることに気付き、生かされている自分であることが本当に分かれば、「摂取不捨」ということが我が身にはたらいていることに気付くことができるのではないでしょうか。
仏教における「真実の教え」は、何ものにも妨げられることのない光としてあらゆる方向に平等にはたらき、いつでもどこでも私たちに届けられています。その光は、私たちの無明を照らし出し、本当の相を顕かにすることとともに、生きることにとまどい、つまずき、傷つき、不安の多い人生の中において、その人生を生き抜く力と勇気、そして励ましと安らぎを与える大きなはたらきになります。
この現代社会を生き抜かなければならない私たちは、時として生きることの厳しさに孤独を強く実感することがあるでしょう。その時は、決して孤独ではなく、他者とのつながりの中に自己を見出し、「どこまでも必ず摂め取って見捨てない」というはたらきに生かされて生きていることに気付かされて、共に乗り越えて行けるのではないでしょうか。(宗教部)
嘘
2019.08.01
人はすぐに嘘をつきます。ひょっとしたら中には、「今まで嘘をついたことがない。」と言う人がおられるかもしれませんが・・・。嘘をつくとどうなるのでしょうか。まず、つじつまが合わなくなります。バレないようにと嘘を重ねると、さらにつじつまが合わなくなり、嘘をつき続けなければならないことになります。そうするとバレないかと常に気になり、精神的に落ち着かず、いつもびくびくした状態で、楽しくない人生になってしまいます。後にバレた時には、時間の経過に応じた不幸が押し寄せてきます。
「嘘つきは泥棒の始まり」、「嘘ついたら針千本飲ます」などのことわざやわらべ歌によって、私たちは小さい頃から嘘は悪いことであるとわかっています。イソップ童話「嘘をつく子供」からは、人は嘘をつき続けると、本当のことを言っても信じてもらえないが、常日頃から努めて正直に生活すると、必要な時に他人からの信頼と助けを得ることが出来るという教訓を学んでいます。最近でも、教訓とすべき世間を騒がすある事件が起こりました。それは、当事者の問題行動はもとより、保身から生まれた「嘘」によって、周囲の信頼を大きく損なうことになり、それが引金となって、人生を変えてしまうまでの事案に発展してしまいました。
では、私たちは実際、日常生活において、嘘をつかずに生きることができるのでしょうか。これはなかなか難しいものがございます。
「嘘」は、仏教では「妄語(もうご)」と言います。「妄語」を諫める「不妄語」は「五戒(ごかい)」の一つとされ、これを破ると八大地獄のうちの大叫喚地獄(だいきょうかんじごく)以上の苦しい地獄へ堕ちるとされており、それほど嘘は恐ろしい罪であると言われています。
お釈迦さまは、「大無量寿経(だいむりょうじゅきょう)」という経典において、私たちの姿を「心口各異、言念無実(しんくかくい ごんねんむじつ)」と説かれています。人の「心と口は、おのおの異なり、言っていることと、念(おも)っていることに、まことがない」という意味で、つまりは、「すべての人は、心で思っていることと、口で言っていることが異なる。だから言っていることにも、思っていることにもまことがない。嘘偽りばかりだ」とおっしゃっています。
例えば、酔っ払って帰ってきた夫が、妻から「あなた、酔っ払っているでしょ」と聞かれると、ついつい「俺は、酔ってないぞ~」と言います。ろれつが回っていないので、酔っていることはバレバレですが、それでも否定したくなって、嘘をついてしまいます。
私たちは、普段あまりにも平気で嘘をついているので、その行為に対し醜いという感覚が麻痺してしまい、嘘という自覚すらないということに気付かなければなりません。そのような嘘偽りばかりの私たちがそのまま幸せになるためには、仏教を聴聞し、愚かな自分に気づかせていただくことを、繰り返し実行するほかないと言えるでしょう。
(宗教部)
学校法人光華女子学園 理事長交代のお知らせ
2019.07.12
学校法人光華女子学園は、2019年7月1日付で阿部 敏行 理事長が退任し、
新たに阿部 恵木 専務理事が理事長に就任いたしました。
(同年5⽉28⽇開催の理事会において決定)
阿部 敏行 前理事長は、引き続き学園長としての任務を継続すると共に、同日付で名誉理事長に就任いたしました。
なお、新理事長 阿部 恵木の略歴は下記のとおりです。
記
○⽒ 名:阿部 恵木(あべ やすき)1971 年8 ⽉19 ⽇ ⽣ (47歳)
○学 歴:大谷大学 文学部 哲学科 卒業
○職 歴:
1997 年 4 ⽉ 学校法人光華女子学園 学園主事
1999 年 6 ⽉ 同 評議員
2000 年 4 ⽉ 同 企画広報室長補佐、
以後、初等中等教育推進部長、KRS推進本部長代理、学園運営部長、宗教部長、新規事業開発プロジェクト部長、総合企画部長、企画広報部長等を歴任
2011 年 4 月 同 学園事務局長
2011 年 6 月 同 理事・評議員
2014 年 4 月 同 専務理事
宝の山に入りて 手を空(むな)しくして帰ることなかれ 『往生要集』 恵心僧都源信
2019.07.01
この言葉は,平安時代中頃の僧で日本浄土教の祖と言われる源信僧都(比叡山の恵心院におられたので恵心僧都とも呼ばれた)の言葉で,その著『往生要集』の中にあります。親鸞聖人はこの源信僧都を,お釈迦さまの説かれた,念仏を唱えることによって阿弥陀仏の浄土に往生するという本願念仏(阿弥陀仏の誓願)の教えを正しく伝えてくださった印度・中国・日本の七人の高僧の六番目・第六祖として尊崇されています。
さて,この源信僧都の言葉は何を教えているのでしょうか。この言葉は,『往生要集』の「大文第一 厭離穢土」の結びにあたる「総結厭相」にあります。源信僧都はこの言葉の前に,人間世界の有様を語っておられます。
それは,今,幸いにして生まれ難い人間世界に生まれきたが,しかし,この世界は変わることのない常住の世界ではなく常に移り変わる無常の世界であり、虚仮の世界である。そうした世界は執着から離れられず,苦しみ・悩む煩悩の世界である,と。しかしいま人間として生まれ,生かされ,仏さまの教えを聞く機会にも恵まれている。この機を逃さず,煩悩に汚れたこの世を離れ,浄土(悟り)の世界に生まれるよう努めるべきである,と言っておられます。そして,その後に「今月の言葉」が続きます。この「宝の山」とは,人間に生まれ,仏さまの教えを聞く機会に恵まれているその「僥倖」をさしているのではないでしょうか。
私はこの言葉から,法会で読まれる「三帰依文」の最初の言葉「人身受け難し,いますでに受く。仏法聞き難し,いますでに聞く。この身今生において度せずんば,さらにいずれの生においてかこの身を度せん。」を思いおこします。光華女子学園は,仏さまの教えを聞く機会に恵まれています。私たちはそうした機会を逃さず,聞思し,手を空しくして終わるような過ごし方をしないようにしたいものです。(宗教部)
メリハリ
2019.06.03
人間は、生きている上でずっと頑張り続けることは出来ないものです。時には頑張り、時にはのんびりと心身を休める時が必要です。
私たちはどうしても日々生活を送る中で、ONとOFFのバランスを見失い、頑張り過ぎたり頑張らなさ過ぎたりすることがあると思います。そうなると心身のバランスが崩れ、健康的な生活を維持することができなくなります。
一つ例えると輪ゴムは、伸縮を利用して、何か物を留めるときに伸ばして使います。その分、輪ゴムは劣化します。さらに、長期間伸ばした状態にしておくと、その劣化は早くなります。しかし、使わないときは、伸びない状態のままですので輪ゴムに負荷はかからず、劣化は防げます。人間も同じで、頑張り過ぎがたたって病気や怪我をしたり、頑張り続けると中だるみしたりします。やはり、メリハリをつけてONとOFFを上手く切り替えることが大切です。
仏教に「中道」という言葉があります。一方にかたよらない穏当な考え方・やり方、執着を離れ、正しい判断をし、行動するという意味があります。
お釈迦様が菩提樹の下でお悟り(成道)を開かれた時、五人の比丘(弟子)に、「比丘たち、出家した者はこの二つの極端に近づいてはならない。二つとは何か。第一にさまざまな対象に向かって愛欲快楽を求めるということ、これは低劣で、卑しく、世俗の者のしわざであり、尊い道を求める者のすることではない。また、第二には自ら肉体的な疲労消耗を追い求めるということ、これは苦しく、尊い道を求める者のすることではなく、真の目的にかなわない。比丘たち、如来はそれら両極端を避けた中道をはっきりと悟った。」と説かれました。(初転法輪)
つまり、私たちは心身とも健康で生きる上で、何事も両極端にするのでなく、一方にかたよらず「バランス」をはかり、「メリハリ」をつけることが大切です。是非一度、自分自身を見つめ直していただく機会にしていただければと思います。(宗教部)