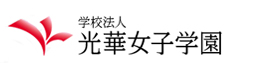彼岸に達する人々は少ない。
他の多くの人々は此岸でさ迷っている。中村元訳(『真理のことば』85)
2002.06.18
彼岸という言葉を人は知っているだろう。しかし、その対極にある此岸を知る人は少ない。彼岸とは、春秋のお彼岸に、亡き近親者を偲ぶように、死者が行きつく所と思われている。それに対して、私たちが今いる所を此岸という。しかし釈尊は、彼岸に達する人々は少ない、と言う。その意味は、死者の誰もが彼岸の世界に到達するのではないということだ。浄土教的に言うと、死ねば誰もが浄土に帰る(還浄)とは限らないということだ。
それは当然のことで、釈尊は此岸の世界でさ迷っているわれわれに彼岸の世界があることを示し、そこに至る方法(道)を説いたのだ。彼岸と此岸を涅槃の世界と生死輪廻する迷いの世界と言い換えると、釈尊は私たち人間を生死輪廻する迷いの世界(此岸)から涅槃の世界(彼岸)へと連れ戻そうとしていたのだ。だから、私たちもいつかその道(それを仏道という)を辿るのでない限り、彼岸に達することはありえないし、何よりも、死ねば誰もが彼岸に到達するというのであれば何も問題はなかったはずだ。
それはともかく、彼岸に達しなかった死者はどうなるのであろう、と疑問に思う人には次のように言っておこう。本当に彼岸(涅槃の世界)に到達するのでない限り、誰もが行きつく死後の世界もまた(それを親鸞は後世と呼んだ)、此岸(迷いの世界)の一つに過ぎないということを。ともあれ、この短い釈尊の言葉の中に、ややもすれば誤解されやすい仏教のエッセンスが纏められている。(可)
つとめ励むのは不死の境地である。
怠(おこた)りなまけるのは死の境涯である。中村元訳(『真理のことば』21)
2002.05.18
社会の、また組織の一員として、人は自らの責任を果たさなければならない。それを人の道と呼んでもいい。しかし、果たすべきはそれだけであろうか。釈尊は人間として生まれた私たちには、もう一つのつとめ励むべき大切なことがあると言う。それを<不死の境地>と表現したが、それを成し遂げてこそ私たちの生にも意味があったといえるものなのだ。宗教(仏教に限らない)とは、この死ぬことのない境地(それを仏教は涅槃(ねはん)、円寂(えんじゃく)、甘露(かんろ)、ニルヴァーナなど、と呼ぶ)を示し、そこに至る道(方法)を説いているのだ。それを仏の道(仏道=大道)と呼ぶならば、仏教の教えに虚心に耳を傾けるものは常に二つの道を見据えながら人生を歩んでいる人と言えるだろう。つまり、誰もが口にする、一度しかない人生を悔いのないように生きるというだけではないのだ。そんなことはあたりまえのことで、言うほどのことでもない。また、それだけのことを言うのに宗教など全く必要ないし、人の道を説くだけで充分なのだ。
しかし、そうでないからこそ釈尊は、後者の道(仏の道)を蔑(ないがし)ろにし、怠りなまけるものは、今生で何を手に入れ、何に成ろうとも、いずれ死とともに失われる儚(はかな)いものに手を染めただけで、ついに<不死の境地>あることを知らず、死から死へと赴く生死の世界(サンサーラ)に空しく往来することになるので、それを<死の境涯>と呼んだのだ。キリスト教ならば「人間は空(から)でこの世に入り、再び空でこの世から出ようとしている」となろうか。(可)
ものごとは心にもとづき、心を主とし、
心によってつくり出される。中村元訳(『真理のことば』1-1)
2002.04.18
『真理のことば』(一般に『法句経』と呼ばれる釈尊の初期経典の一つ)の冒頭を飾るこの文章の中に人間存在の基本原理が簡潔に表明されている。ものごととは、私たちが毎日経験し、また目にしている生死・善悪・愛憎・苦楽・幸不幸・・・の悲喜劇すべてをいう。そして、これら二元性は私たち自身の心から生じてくるというのだ。とりわけ意外に思われるかもしれないが、生死さえ心より起こるのだ。しかし、仏教はこの二元葛藤するサンサーラの世界(生死輪廻する世界)にあって、いかにうまく世渡りをし、生き延びるかを説いているのではない。むしろ、これら二元性が生じてくる心に誑(たぶら)かされ、どちらにも執着してはならないと教えているのだ。さらに言うならば、心によって私たちは天国から地獄までも作り出すが、夢(心が投影したもの)に実体がないように、いずれも幻影の世界であり、人間界もその一つに過ぎないのだ。だからと言って、釈尊をはじめ、古の聖賢たちはこの世界を離れたどこかに二元性を超える一真実の世界を求めたのではない。要は、心が消え去るならば、生死をはじめとする二元葛藤する世界はあるだろうかということだ。果たして、心を除き、真理に目覚めた覚者(仏陀)たちの目に、この世界はどのように映っていたのであろうか・・・。(可)
我々は常に、
信ずるは力なりということを忘れてはならぬ。(清沢満之「信ずるは力なり」)
2002.03.18
これまで様々な主義・主張(イデオロギー)が立ち現れては消えていった。それだけではなく、一人の人間を捉えた妄信が狂気となって全世界を巻き込む混乱と殺戮の引き金となったことは歴史を少し紐解けば明らかである。そこには奢り高ぶった人間(あるいは国家)の傲慢が見え隠れするが、彼らに欠けているのは、人間とは、あるいは自己とはいかなる存在であるかという認識の欠如である。その点、浄土の思想家たちは、深く自らを顧み、現在私たちが立ち至っている現状を明確に自覚すると共に(それを「機の深信」という)、いかにすれば真実に叶った生となり得るかを謙虚に学んできたと言えるだろう(同様に「法の深信」という)。このように、信じることには二つあるのだが、何よりもわれわれ一人ひとりが前者に深く思いを致し、自己(機)を顧みるのでない限り、今日そうであるように、人心も世情もいたずらに混乱するばかりで、決して真実なるもの(法)は見えてこないであろう、と説いているのが仏教なのだ。(可)
宇宙万有の千変万化は、
皆これ一大不可思議の妙用に属す。(清沢満之「絶対他力の大道」)
2002.02.18
古今東西を問わず、いわゆる聖賢(せいけん)たちは、一様に千変万化する宇宙の存在の奥に何があるのかを知ろうとして真理の探求を始めたようである。そして彼らは、一瞬の光芒(こうぼう)の中で、私たちが目にしている現象世界の背後に、新たな存在の次元を垣間見たのではないか。それだけではなく、人為を超えた、自然に在らしめられるその世界と一つに溶け合い、抗(あらが)うことなく漂う術を知ったようである。この時空を超えた永遠の世界を親鸞は<自然法(じねんほう)爾(に)>の世界と表現し、それを体して生きることが、人間として生を享(う)けた私たちの存在の意味であり、また真に創造的な生を生きることにもなる。しかし、そのために私たちは自らの実存をしっかりとその存在世界に根付かせることが必要なのだ。というのも、現在の私たちは、あたかも定めなく漂う根無し草のようなものであり、とうてい存在の神秘(一大不可思議の妙用)を知りえない無明存在であるからだ。(可)
万物一体の真理は、吾人がこれを覚知せざる間も、
常に吾人の上に活動しつつあるなり。(清沢満之「万物一体」)
2002.01.18
百数十億年前に起こったビッグバンからこの宇宙は始まったと現代の科学者は言う。人間もかつては宇宙の塵に過ぎなかった。それが植物界へと出、植物界から動物界を経て人間界へと進化してきた。その意味するところは、人間はこの進化の過程すべてを包摂しているだけではなく、存在するすべての物に支えられて存在しているということだ。
私たちは人間も含め、万物が相互に関係しながら存在していることを覚らなければならないが、禅はその体験を万物同根と表した。個々ばらばらに見えている人、物、自然、すべてがその根底において一体であるという宗教体験から私たちは本当の意味で愛(慈悲)とは、非暴力とは何かを知ることになる。しかし、今のところ私たち人間はその認識に到達していないために、環境の破壊はますます進み、また仮想の敵を想定して相争っていることは、昨今の世界状況を見れば明らかである。(可)
我、他力の救済を念ずるときは、我が世に処するの道開け、
我、他力の救済を忘るるときは、我が世に処するの道閉ず。
(清沢満之「他力の救済」)
2001.12.18
「他力」とは「自力」に対するもので、私たちを無条件で生かしている大いなる力ということができる。自己の立脚地をこの大いなる力の上に置くとき、我々はおのずとこの世での自らの役割を見出し、それに邁進する道が与えられるのである。
しかし自我に閉ざされ、他に抜きん出て利得をむさぼろうとするとき、我々はたちまちにして閉塞的な状況に転落する。自力は時として他者との関係を切断し、我々が本来与えられている生への意欲をも削ぎ取りかねないのである。
いま一度、深く内省することによって、永遠の過去・無限の彼方からなる大いなる力に立ち返り、この世に処する道を真摯にたずねたいものである。
吾人の世に在るや、
必ず一つの完全なる立脚地なかるべからず。(「精神主義」)
2001.11.18
齢80になろうとする釈尊が弟子のアーナンダを伴ってある村に滞在していた。45年の永きにおよぶ教化の旅もようやく終りに近づき、その地で彼は弟子達に対して最後の説法をすることになる。それはおよそ次のようなものであった。「この世で自らを島とし、自らを拠り所として、他人をたよりとせず、法を島とし、法を拠り所として、他を拠り所としてはならない」(漢訳で「自帰依・法帰依」とまとめられているもの)。宗教は、問われるべきは自分自身であること、また問題があるとすれば、他でもない自分自身にあることを強く言う(もっとも、殆どの人にとって問題がどこにあるかが分かっていないのだが)。他者を批判する前に、まず自らを省み、自らを深く探求することの中に生の意味は明らかになると宗教は教えているのだ。そして、その意味とは<生死の苦海>(親鸞の言葉)に浮沈する私たち自身の中に本当に依るべき不動の真理が隠されているということだ。この依るべきところを釈尊は「島」と言い、依るべき真理を「法」と呼んだのである。それこそ私たちの立脚地であり、それを知りさえすれば、もはや私たちは生死の波に翻弄されることはない。
生のみが我等にあらず。死もまた我等なり。(「絶対他力の大道」)
2001.10.18
私たちの住むこの世界は生死・善悪をはじめとする二元相対の世界をなしている。生死を例にとれば、私たちは生のみに意味と希望を見出し、死はできるだけ遠ざけようとするが、死を遁れることは誰にもできない。しかし、これだけのことを言うのに、わざわざ宗教を持ち出すこともない。それは誰にとっても明白なことであるからだ。
では、宗教とは何かと言えば、喜びをもって抱きとめられた生が、いつしか悲しみの涙に看取られつつ、ひとり死出の旅へと赴く、この矛盾を問題にしているのだ。それは、生老病死の問題を引っ提げて出家した仏教の開祖釈尊は言うまでもなく、その法(教え)を受け継いだ多くの宗教的天才と呼ばれる人たち(親鸞、道元、空海など)も、この矛盾と悲しみを直視した人たちであったことを私たちは忘れてはならない。そして、この避け難い現実を見据え、彼らが一様に求めたものは、親鸞の言う<生死出ずべき道>であったのに対して、私たちはと言えば、「生死の苦海を出離せんことを求めず」(慧能『六祖壇経』)、ただ生まれたといっては喜びの涙を流し、死んだといっては悲しみの涙を流しているだけなのだ。
請う勿れ、求むる勿れ、
なんじ、何の不足かある。(「絶対他力の大道」)
2001.09.18
仏法を求めるとは一体どういうことであろうか。それを知るために『法華経』の中に説かれている「長者窮児の譬え」がヒントになるかもしれない。長者とは父を窮児はその子を意味しているが、実は「長者は自ら財宝、無量なり」と言われるように仏を象徴しています。その子である私たちは(一切衆生は皆、これ吾が子なり)、父の家(仏の家)を離れて三界生死の世界をさ迷い、さながら乞食のように、あれもこれも手に入れようとするが、いつも何かが欠けているのだ。
長者の家の子となりて
貪里に迷うに異ならず
この貪里(私たちが今いる娑婆世界のことであり、また火宅の世界とも言う)に迷う欠乏を裏返したものが欲望であり、その欲望と不満は私たちが父の家に帰り着くまでなくならない。そして、父の家とは実は私たち自身の内側であり、真理(仏法=仏性)はすでに私たちに具わっている。つまり、私たちに欠けるものは何もないということだ。この円に具わる内なる真理を親鸞は「功徳の宝海」と呼び、禅の思想家馬祖は「自家の宝蔵」と呼んだ。すると、仏法を求めるとは、何ら欠けることのない私たち自身の内なる真実に気づくことであり、その時すべての欲望は消え去り、少欲すらもないというのが、仏教に限らず宗教一般の体験なのである。