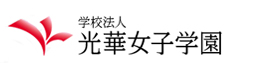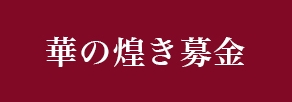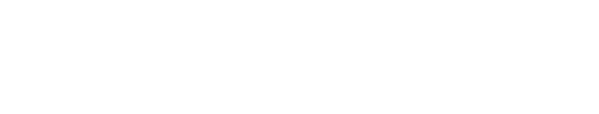「濁る」で思いつくのが、日本語の濁音(だくおん)である。「かき(柿)」と「かぎ(鍵)」や「ふた(蓋)」と「ぶた(豚)」ように濁点「〝」の有無によって全く別の言葉になってしまう学びは、小学校を入学したての「ひらがな学習」の一環として1年生は、国語の教科書に学んでいく。
たまたま道を歩いていると、お寺の掲示板が目に止まった。「口が濁ると愚痴となる」と・・・。「誰の言葉だろう」と気になり、検索してみると、この言葉には続きがあった。
口が濁ると愚痴となり/意志が濁ると意地となり/才が濁ると罪となり/徳が濁れば毒となり/
戒が濁れば害となり/本能が濁れば煩悩となり/報恩が濁れば忘恩となる。あな恐ろしや人の濁りは!
結局、誰の言葉かは分からなかったが、小学1年生で習う濁点「〝」の有無によって全く別の言葉になる学びは、幼少の時を超え「ドキッ」と我が身の胸に突き刺さった。
今月の言葉「濁世の目足」は親鸞聖人の言葉である。親鸞聖人は濁世の中で、生きられた方である。
地震や大火などがあいつぎ、さらに飢饉や疫病などのために、死者が都にあふれ、その死臭が人々の不安をいっそうふかいものにしていた。誰も彼も、悲しみや苦しみに耐えながら、その日一日を生きぬくことに精一杯であった。『宗祖親鸞聖人』(東本願寺)
現代社会における濁世とは何か。様々な社会問題が複雑に絡み合い、人々の生活が困難になっている状況を指す言葉として使われることが多い。例えば、貧困、少子高齢化、環境問題、格差、紛争など、多岐に渡って挙げられる。濁るということは、大事なものが見えにくくなるということである。水槽の水が濁れば、中の魚も見えない。あらゆる情報の中で、世間の価値に一喜一憂しながら、煩悩を抱える私は、世の中の濁りは中々見えないし、濁っていることにも気がつかないのである。
「濁世の目足」とは、先の見えない不安な世の中を歩んでいくための、目となり、足となるということ。濁世の中におって、本当に正しいものを見る目をいただく、そして厳しい現実を歩む足をいただく。親鸞聖人は、その目と足を、お念仏の世界だと教えてくれる。どんな時代や境遇においても、世間の価値に振り回されて生きる私を受け入れながら、仏の教えに聞き、目と足をいただいていきたいものである。
過去のことば
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年