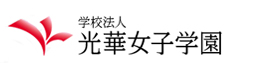眠れる者たちの中にあって、
よく目覚めてあれ。中村元訳(『真理のことば』29)
2003.04.18
仏教は目覚めの宗教であると言われる。悟りを開いた釈尊を、真理に目覚めた人という意味で、覚者と呼ぶのもそのためである。一方、眠れる者とはわれわれ人間を指しているが、その私たちに彼は、よく目覚めてあれ!と注意を促しているのだ。
その真意を問う前に、真理に目覚めるとはどういう体験をいうのであろうか。それは夢の眠りから目覚めるようなものと言えるだろう。というのも、夢の中を彷徨っていた者が目を覚ますと、夢は消え、現実(日常)に戻るように、この現実という夢(それを老子は「大夢」という)から目覚め、もう一つの現実(真理)を知ること(同じく「大覚」という)であるからだ。つまり、釈尊は、私たちは眠りにつくと夢を見るが、私たちが現実と見なしているこの世界もまた夢のようなものと解しているのだ。それは仏教に限らず、宗教的覚醒を得た、いわゆる覚者たちは一様に「この世は夢の如し」(ルーミー)と言う。
すると、目覚めには二つある。一つは私たちがよく知っている、夜の眠りから目覚め、新たな一日が始まるというものだ。この日々の繰り返しが生(人生)に他ならないが、この全体が夢の如きものであると説いているのが宗教なのだ。それに対して、夢の延長に過ぎない、いわゆる現実(日常)から更に目覚めることによって見えてくる真実の世界(真理)があるのだ。釈尊が、眠れる者たちの中にあって、よく目覚めてあれと言うのも、後者を指しているが、夢を見るのは、いずれにせよ眠れる者に限られるからだ。そして、真理(真実の世界)は、私たちが悟ろうが、悟るまいが、法(ほう)爾(に)として常に存在し、それを空海は「法然の有」と呼び、親鸞は自然法(じねんほう)爾(に)の世界と言う。(可)
無明こそ最大の咎(とが)である。
それを除き去れ。中村元訳(『真理のことば』243)
2003.03.18
生まれること、そして老死が避けられない根本原因に何があるかを探った釈尊が、行き着いた結論は無明にあった。無明こそ最大の咎であると言われる所以である。逆に言うと、無明を除くことができたら、生・老死という迷いの生存(世間)を離れることになろうというのが、仏教が説く縁起の法(法則)である。
無明とは真理に暗いということであるが、その真理を覚ったものを覚者、すなわち仏(たとえば、釈迦牟尼仏など)と呼ぶのに対して、それを知らず、生々死々を繰り返している私たち人間を「迷道の衆生」という。ところで、学問もまた知識や技術を習得し、真理の探究に努めることであると言われる。しかし、ここでいう真理は仏教が説くそれではない。それ故、新たな発見や学問の進歩にどれだけ寄与したとしても、それが生死の根源にある無明を除くことには繋がらない。というか、もとよりそんなことを問題にしているのでないから当然であるが、では、無明を除くために何が必要なのであろうか。
無明(avidya)の対概念は明(vidya)であって、決して多知多解(多くを知り、多くを理解できること)ではない。無明を除くために必要なのは光明であり、宗教とは、真っ暗な部屋に一条の光が差し込むと、忽ちその全体(存在のリアリティ)が露になるような体験と言えるかもしれない。親鸞は、この無明の闇を照らす光を智慧の光明(無量光・無辺光)と呼び、私たちもまたその光に出遭うならば、生死・善悪を初めとする二元相対の世界(世間)を離れ、終には仏に成るとした。(可)
世の中を泡沫の如く、陽炎の如くと見よ。中村元訳(『真理のことば』170)
2003.02.18
釈尊が悟りを開いた時、彼は一体何を知ったのであろうか。その答えの一つが、この世のすべては泡沫(うたかた)の如く果敢なく、また陽炎(かげろう)の如く実体がないということであった。しかし、身体も含め、私たちが目にし、触れるものはもちろん、日常的に経験する喜びや悲しみに実体がないとは誰も思っていない。それどころか、「鏡中の像」のように実体がないものに、私たちは心奪われ、あれもこれも手に入れようとして、かえって多くの問題を抱え込み、一喜一憂しているのではないか。
否、問題はそれだけではなかった。ことは私たちの生存(生と死)にまで及ぶ。なぜなら、釈尊はこれに続いて「世の中をこのように観ずる人は、死王も彼を見ることがない」と付け加えているからだ。その意味は、この世を陽炎の如く実体はないと本当に知った(覚った)人は二度と死の憂き目を見ることがない。つまり、この生存が、この肉体が「最後の身体」であるとはっきりと知っているということだ。
逆に言うと、この世の様(さま)を実体的に捉えている限り(現在、私たちはそうしているのであるが)、生死の絆を断ち、涅槃(悟り)の世界に趣くことはできないということだ。すべてはヴァーチャル(仮有実無)にしか存在しないにもかかわらず、それに囚われていく妄執ゆえに、私たちはそうと気づくこともなく、迷いの生存を繰り返すことになるからだ。「生存に対する妄執を滅ぼし、実体についての固執を断ち切った修行僧にとっては、生まれを繰り返す輪廻が滅びている。今や迷いの生存を再び繰り返すことはない(ウダーナヴァルガ)」。(可)
作られざるものを知り、
生死の絆を断った人こそ最上の人である。中村元訳(『真理のことば』97)
2003.01.18
生きる上で、私たちは何を判断の基準とすればいいのだろう。その一つに、それが作られたものか(と言っても、私たちが知っているものはすべてそうなのだが)、作られざるものかということが挙げられよう。作られたものには始まりがあり、始まりがあるものには必ず終りがくる。この始まりがあり、終りがくるものに執着し、囚われてはならないと教えているのが仏教なのだ。一例として、私たちが生命と呼んでいるものがある。いのちと言えば、私たちは作られたものとしての肉体の生命しか知らない。もちろん、この生命には始まりがあるが故にいつか終りがくる。この悲しみを私たちは何度も経験してきたというので仏教は、今、私たちが居るところを生死の絆に縛られ、生々死々を繰り返している輪廻の世界(サンサーラ)と呼ぶ。それに対して、作られざる涅槃の世界(ニルヴァーナ)もあると説いているのが仏教なのだ。だから仏教の開祖である釈尊は、生死の絆を断ち、作られざる不生不死の境地(生まれることもなければ、死ぬこともない境地)を知った人こそ最上の人であるとしたのだ。
すると、私たちが辿るべきは作られたものから作られざるものへ、死すべきものから不死なるものへということになろう。この始めもなければ終りもない永遠のいのちを知って初めて私たちは真に安らぐのであり、そういう人を釈尊は<最上の人>と呼んだのだ。しかし、それは他者と比較して優れているというのではない。永遠のいのちに目覚め、不安なく、恐れなく、どんな状況にあっても自らを信頼し、生を歩んでいる人ということだ。そして、今生において、生死の絆を断つかどうかはあなた次第であり、それを親鸞は<滅度>に至ると言ったのだ。(可)
仮初(かりそめ)の身に等しい
苦しみは存在しない。中村元訳(『真理のことば』203)
2002.12.18
仮初の身とは、生まれ、やがては老死に向かう生命を指している。それを釈尊は生・老・病・死の四苦と捉え、それが彼に出家を促したと歴史は伝えている。しかし、数年の求道を経て、仮初の身を直視する彼の前に、突如として、朽ちることのない永遠のいのちが開示されることになるのは、「この理をあるがままに知ったならば、ニルヴァーナ(涅槃)という最上の楽しみがある」と続いていることからも分かる。
われわれが生命と呼んでいるものは、生じては消える波のようなものなのだ。波が海から生じ、一時海に支えられ、再び海に消え去るように、われわれの生命もまた永遠なるいのち(それを浄土教は無量寿仏、即ち阿弥陀仏と呼び習わしてきたのだ)に支えられている。さらに、生だけではなく、死もまた永遠なるいのちが存在してはじめて起こり得るのだ。キルケゴールが「死もまた一切のものを包む永遠なる生命の内部における小さな出来事であるに過ぎない」と言った意味もここにある。
そして、この事実は、生命の本質はただ生じては消える波を見ているだけでは明らかになってこないことを示している。私たちはその本質を知るためにも、それらの根源に繋がるものを見届けねばならないのだ。百数十億年をかけて進化を遂げてきた宇宙の塵(屑)に過ぎない生命を内側深くへと辿ることによって、私たちはその本源に繋がる永遠なるいのちそのものを知ることができるのだ。しかし、自らを波と見なし、自分を取り巻くさまざまな波に伍して、自分にエネルギーを注ぎ続ける限り、つまり自力を恃み(たの)、自我を貫き通す限り、あなたは波としての生命しか知らず、いつまでも生死の波に翻弄されることになる。(可)
自己こそ自分の主である。
他人がどうして自分の主であろうか。中村元訳(『真理のことば』160)
2002.11.18
社会の中で多くの人々に伍し、自分が立ち行くために、まず自己を確立し、自律することが求められてくる。教育もその一助となっていよう。しかし、それだけのことを言うのに仏教(広くは宗教)など必要ない。事実、釈尊は今のあなたが主(それは自我でしかない)であるとは言っていない。むしろ、私たちが自分と呼びならわしている自己が良くも悪くも多くの問題を生み出し、煩いと混乱を来たしているのだ。だから仏教は、そういう自分を<世俗の我>と言い、それに対して<真実の我>もあるが、それを知る人は、実は極めて少ないのだ。それは、この文章の後に、彼が「自己をよく整えたならば、得難き主を得る」と条件を付けていることからも分かる。ありていに言えば、私たちは未だ本当の主(真の自己)を知らないだけではなく、エゴ(自我)に過ぎない自分を私と見なし、時に談合し、また相争っているのだ。
この得難き主を知ってはじめて私たちは自分の主となる。しかし、そうできなければ、人はそうと気付くこともなく、物心両面で他者(組織)に隷属し、不安と孤独、葛藤と虚しさは死ぬまで無くならないであろう。宗教は一見すると、神や仏の信仰のごとく見られるが、真の自己(それを禅は「本来の面目」と言う)を知り、自らの主となることを説いているのだ。そして、それを知るのはあなたを措いて他に誰もいない。
自己を整える方法は宗教によって様々であるが、釈尊が苦行を捨て、菩提樹の下で禅定(三昧)に入り悟りを得たように、それらの総称が瞑想と言われているものである。親鸞が採った方法が念仏(三昧)であったことはいうまでもない。(可)
私は幾多の生涯にわたって
生死の流れを無益に経巡ってきた。中村元訳(『真理のことば』153)
2002.10.18
私とは仏教の開祖釈尊を指している。六年の修行の末に、悟りを開いたとされる彼が、やがて人々に法(真理)を説く旅に出、自らの過去を振り返って語られた言葉の内容は意外なものであった。というのも、王子として生まれた彼が、これまでにもいろんなものに生まれ、何度も死の苦しみを味わってきたと言うのだ。
私たちは生を「一生」と考えるが(ある意味でそうなのだが)、釈尊は「幾多の生涯」と言う。しかも、彼は無益に生と死を繰り返してきたというのだ。もちろん、私たちも例外ではなく、始めとて分からない遠い過去から、いたずらに世々生々を繰り返してきたということだ。しかも、私たちが生死に迷う衆生であるとの自覚もないまま、輪廻転生を繰り返していることを知らせんがために、釈尊は自らの出自を例に出したのであろう。
すると、ここに死し、かしこに生き(空海の言葉)、生死の流れを無益に経巡(へめぐ)っている私たちが目指すべきは、この生死の獄(同上)から如何にして離れるかということになるであろう。それは『歎異抄』に「われもひとも、生死をはなれんことこそ、諸仏の御本意にておわしませば」とあることからも明らかである。そして、この生死の流れを渡り切ったところを仏教は彼岸(涅槃)と呼ぶが、過去に輩出したであろう幾多の仏たちは、空しく生死の波に翻弄される私たちを生死輪廻する世界(此岸)から涅槃の世界(彼岸)へと連れ戻そうとしているのだ。(可)
心を制する人々は、死の束縛から逃れるであろう。中村元訳(『真理のことば』37)
2002.09.18
心の教育ということが言われて久しいが、掛け声のみあって、実をあげたという例を寡聞(かぶん)にして耳にしたことがないのは、私だけだろうか。行為には身・口・意(心)の三業があり、それぞれに善悪があるが、その基本は心(意)であるから、心を問い直すのは自然なことである。
しかし、釈尊の言葉を見る限り、心が一般に考えられている行為の基本にとどまらず、生死の問題と関係していることが読み取れるであろう。しかも、心を制する人々は、死の束縛から逃れるであろうと言うのであるから、そうできなければ、生々死々(輪廻(りんね)転生(てんしょう))は果てしなく続き、生老病死の四苦から逃れられないという含みがある。生(誕生)と死という、私たちの意志や努力ではどうしようもないと思われる出来事が、自分の心と深く関係していることが分かるであろう。心というものが、心理学の狭い理解を超えて、私たち自身の存在といかに深く関わっているかを示す典型的な例と言える。
さて、仏教は心を真心と妄心の二相に分けるが、妄心とは、文字通り、妄(みだ)りに起こる心という意味である。といっても、私たちが普通に心と呼んでいるものであり、心理学が扱っているのもこの心なのだ。もちろん、私たちが今生きているのは妄心であり、その心ゆえに私たちは徒(いたずら)に生まれ、徒に死を繰り返しているのである。一方、真心(真実心)とは、その妄りに起こる心を制し、生死の絆を離れ真実の世界へと帰っていく人々をいう。親鸞は彼らを<正定聚(しょうじょうじゅ)不退(ふたい)の人>と呼んだが、もはや再び生死の陥穽(かんせい)に落ちることのない人という意味である。(可)
正しい真理を知らない愚か者には、
生死の道のりは長い。中村元訳(『真理のことば』60)
2002.08.18
学問は真理の探求であるといわれるが、それに従事するものが仏教の主要なテーマである生死の問題を念頭においているとはとても思えない。むしろこの言葉から、物知り顔に振舞う人間の愚かさを、釈尊は暗に批判しているように感じてしまうのは私一人であろうか。
それはともかく、真理には正しい真理とそうでない真理の二種類があるようだ。そして、正しい真理を知らない者を愚者というなら、それを知る者を賢者と呼んでもいい。また、愚者にとって、生死の道のりは長いと彼は言うのだから、賢者には短いということになるだろう。
さて、長寿を全うすることは、人間的に言えば、慶ばしいことであるが、生死の道のりは、愚者にとって、長いというのであるから、歓迎されるどころか、大いに問題があることを示している。それは親鸞や道元が言ったように、いくたびか徒(いたずら)に生まれ、徒に死を繰り返してきた私たちが、今生において、正しい真理を知るのでなければ、生々死々はいつ果てるともなく続いていくことになるので、生死の道のりは長いと釈尊は言ったのだ。一方、幸いにも、それを知った賢者はもはや再び生を享けることはなく、この生存が最後となる。仏教において、愚者と賢者を分けるのは、いわゆる知識(情報)の多少ではなく、正しい真理を知っているかどうかであることを銘記しておこう。
生死の苦海に身を淪(しず)める私たち人間にとって、本当に知るべきことは多くない、ただ一つである。それを仏教は真知(無著(むじゃく)の言葉)といい、また正しい真理ともいうが、仏とはその真理に目覚めた人のことであり、この真理によって幸せであれ!と教えているのが仏教なのだ。(可)
われらはここにあって死ぬはずのものである、
と覚悟しよう。中村元訳(『真理のことば』6)
2002.07.18
われわれの未来に何が起こるかなど誰にも判らない。確実なことはただ一つ、死だけであり、死のみが保証された生を、今私たちは生きている。さらに言えば、現下、不治の病と戦っているものだけが死の床にあるのではない。どんな人も生まれ落ちたその時から、一瞬たりとも死の床を離れたことがない。それにもかかわらず、多くの人々は死についてあまりにも無関心に過ぎるようだ。しかし、この避けようもない事実を忘れないものしか真に宗教の世界に入ることは難しい。というのも、その覚悟があってはじめて私たちは古(いにしえ)の聖賢(覚者)たちが辿った同じ出発地点に立つことになるからだ。
死をタブー視し、死から目を背けていては(現在、私たちは無意識のうちに、そうしているのであるが)、ただ老死へと行き着く生を知るばかりで、生の本当の意味は見えてこないだろう。なぜなら、生の意味は死の彼方に拓(ひら)かれてくるものであり、私たちは生に執着するあまり、死をできるだけ遠ざけようとするが、そうではなく、一度は、死について深く瞑想し(思いを致し)、その深淵に自らを解き放つ時、はじめて死をも超える「不死の境地」(5月の言葉を参照)あることを知るのだ。
この死から始まる生(浄土教はそれを「前念命終・後念即生」という)の中に、時空を超えた存在の輝きと創造があり、それと一つになることが、ここまで進化を遂げてきた人間に残された唯一の可能性なのだ。(可)