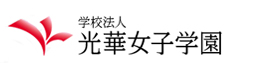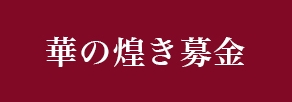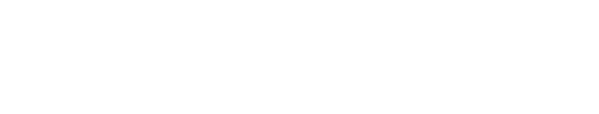新型コロナウイルスワクチン2回目接種完了
2021.08.06
本学園は、8月5日(木)・6日(金)の2日間、医療現場への実習を控えている看護学科・助産学専攻科の学生と教員の希望者323名に対して、新型コロナウイルスワクチン接種2回目を実施いたしました。
7月8日(木)・9日(金)に実施した第1回目と同様に、学内教職員で組織する新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム中心の運営で行いました。コロナ禍での「密」を回避するため、受付時間の分散や検温・消毒などの事前受付の設置など工夫し、ソーシャルディスタンスを確保することで、接種対象の皆さまが安心・安全に接種を受けられるような環境整備に努めました。
当日の接種オペレーション(受付、予診票確認、予診、薬液充填・充填チェック、接種・接種補助、接種後経過観察)は、医師免許・看護師資格を有する本学教員および関係医療機関のご協力のもと行いました。
今回の2回目ワクチン接種においても、重篤な副反応を発生する学生や教員はおらず、無事に終えることができました。
なお、大学生・短期大学生・大学院生および教職員等を対象とした大学拠点接種の第1回目は、8月24日(火)・25日(水)に実施いたします。
今後も安心・安全な教育環境の実現に努めてまいります。
【本件のお問い合わせ先】
学校法人光華女子学園
新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム
[E-mail] vaccine@mail.koka.ac.jp




学園創立80周年記念事業「学園オリジナルグッズ」商品化最終報告会を開催しました
2021.08.02
本学園は2020年に学園創立80周年を迎え、在学生(在校生・園児)が参加できるイベントを開催し、学園創立80周年の節目に、今後長く活用できるオリジナルグッズを制作することで、学園創立80周年を全員でお祝いすることを目的として、学園に在籍する学生・生徒・児童・園児を対象に「学園オリジナルグッズアイデアコンテスト」を開催いたしました。
受賞企画の中から商品化に向け、ライフデザイン特論の受講生やライフデザイン学科・健康栄養学科の学生有志による検討チームを編成し、活動を行いました。
学生たちはコロナ禍でオンライン授業に切り替わり、対面での打ち合わせが難しく、準備期間も限られた中で、商品化に向けたマーケティング分析、連携企業への提案や調整などを主体的に取り組みました。
7月20日(火)に開催した「学園オリジナルグッズ」商品化最終報告会では、各チームともオリジナリティ溢れるプレゼンテーションを披露し、厳正なる審査の結果、短期大学部 ライフデザイン学科の学生リーダー組織「D‘*Light」より提案された「お香」が商品化されることが決定いたしました。
この企画は、「学園オリジナルグッズアイデアコンテスト」グッズ部門で優秀賞を受賞された高等学校3年生(受賞当時の学年)の清水 桃さんのアイデアをもとに、D‘*Lightのメンバーが「香りにのせて思い出を~80年の時間を銘記する」という想いのもと、真宗大谷派の宗門校である本学園に合った商品として提案されました。
今後、10月30日(土)に開催を予定している学園創立80周年記念式典での配布を目指し、皆さまにとって心に残る記念品となるよう制作を進めてまいります。
*D‘*Light:ライフデザイン学科の有志で集まった学生が中心となり、学内外でのイベントの企画・運営など、さまざまな活動を行う団体

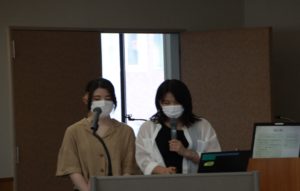


自灯明法灯明
2021.07.09
釈尊は死期が迫ったときに「自らを拠り所(灯明)とし、法を拠り所(灯明)としなさい」と弟子たちに説いたとされています。釈尊最後の旅路を描く「大般涅槃経」の一節としてよく知られていますが、今回は「転輪王経」を手がかりに考えます(長部26経、片山一良『長部』第5巻)。
本経で、釈尊は最初に自灯明法灯明の教えを示した後に転輪王について語りはじめます。転輪王とは古代インドで伝承される、武力に頼ることなく全インドを治める理想の王です。王位は相続されますが、天界に属する輪宝が輝いた者が転輪王となるのであって、相続されるものではないとされます。
昔ダラネーミという転輪王が登場しその国では七代に渡って転輪王の治世が続き、人々は繁栄し幸福に暮らしていた。しかし七代目の転輪王の息子は転輪王にはなれず、徐々に国は衰退、人々は荒廃して互いに傷つけ合うようになったと釈尊は語ります。転輪王になった王となれなかった王との違いをこの経典はどのように描いているのでしょうか。
転輪王は輪宝が陰ると、自ら退位し王位を息子に譲り出家します。後に転輪王となった王たちは、王位に就いたものの輪宝が消えたことに不安を感じ、出家した父王に尋ねに行きます。父はまず自分自身が転輪王として振る舞うことが必要だと教えます。社会のさまざまな立場の人、そして動物たちを「法」に基づき統治し、「法」に背く行為をなさず、貧しい者に施しをすること。そして、時に応じて賢者たちに、善とは何か不善とは何か、罪とは何か、何に従うべきか何に従うべきではないかなどを問うことが転輪王の務めなのです。転輪王となった王たちはこれを実践することで転輪王となりました。
これに対し転輪王になれなかった王は、王位に就いた時に輪宝が消えていても、父王に尋ねに行きませんでした。そして「自分の考え」で統治を行ったと経典は語ります。「自分の考え」と言っても、何かおかしなことをしたわけではありません。大臣たちがアドバイスをすればそれを受け入れ、むしろ本人としては一生懸命、務めを果たそうとしています。盗みを働いた者がいれば理由を尋ね、困窮していることがわかると諭し財を与えます。しかしそうすると、財目当てで盗みを働く者たちが出てきました。すると、王はそれに対応するために厳しい罰を与えることにしました。その噂はすぐに広まり、人々は嘘をつくようになりました。こうして少しずつ社会は崩れて、人々は疑心暗鬼にかられ荒廃していきます。倫理が崩壊したさまを「人の寿命は10歳になり、5歳の少女が結婚する」と経典は表現しています。
必死に対応しようとするこの王に足りなかったものこそが、「法に基づく」(法灯明)だといえます。それは、賢者たちに善とは何か等と問うこととも関係しています。つまり法灯明とは、目の前の現実に対応しようとする自分の価値観や考え方そのものを検証する姿勢、視点といえます。
これは王や為政者のみに限りません。本経には相手を野獣とみなし殺し合っていた者たちが、人を殺すのをやめようと各自森などに潜み、7日後に「ああ、あなたは生きている!」と相手の生存を喜ぶ場面があります。相手に対する不安や恐怖にかられている「自分の考え」から解放されることで、他者の幸福を喜ぶ自分を見いだし、そこから社会が回復していく様子が描かれています。
不安な時代が続きます。今を乗り切るために必要なのは、自分の不安に飲み込まれない自分を見る視点を育てていくことなのかもしれません。(宗教部)
新型コロナウイルスワクチン1回目接種完了
2021.07.09
本学園は、7月8日(木)・9日(金)の2日間、医療現場への実習を控えている看護学科・助産学専攻科の学生と教員の希望者324名に対して、新型コロナウイルスワクチン接種1回目を実施いたしました。
事前に新型コロナウイルスワクチン接種対策チームを中心に、運営方法の打ち合わせやリハーサルを行いました。また、コロナ禍での「密」を回避するため、受付時間の分散や検温・消毒などの事前受付の設置など工夫し、ソーシャルディスタンスを確保することで、接種対象の皆さまが安心・安全に接種を受けられるような環境整備に努めました。
当日の接種オペレーション(受付、予診票確認、予診、薬液充填・充填チェック、接種・接種補助、接種後経過観察)は、医師免許・看護師資格を有する本学教員および関係医療機関のご協力のもと行いました。接種前は緊張していた学生たちも本学教員が声かけを行うことで、安心して接種を受けることができました。
1回目のワクチン接種においては、重篤な副反応を発生する学生や教員はおらず、無事に終えることができました。
なお、2回目の接種は、8月5日(木)・6日(金)に実施いたします。
今後も安心・安全な教育環境の実現に努めてまいります。
【本件のお問い合わせ先】
学校法人光華女子学園
新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム
[E-mail] vaccine@mail.koka.ac.jp






新型コロナウイルスワクチン接種の実施について
2021.07.06
本学園は、このたび医療現場への実習を控えている看護学科・助産学専攻科の学生と教員を対象とした新型コロナウイルスワクチン接種を以下の日程で実施いたします。医師免許・看護師資格を有する本学教員および関係医療機関のご協力の下、安心、安全な接種体制で実施いたします。
今後は、順次、本学学生・教職員等への接種機会の拡大に努めていきます。
1.実施期間: <第1回目接種> 2021年7月8日(木)~7月9日(金)
<第2回目接種> 2021年8月5日(木)~8月6日(金)
2.実施会場: 京都光華女子大学 瑞風館1階
3.接種対象: 看護学科・助産学専攻科の学生、教員で希望した者
4.ワクチンの種類:ファイザー社製ワクチン
【本件のお問い合わせ先】
学校法人光華女子学園
新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム
[E-mail] vaccine@mail.koka.ac.jp
【重要】新型コロナウイルスワクチン予防に係る職域接種の実施(保留)について
2021.06.25
6月22日にご案内いたしました新型コロナウイルスワクチン職域接種について、既に本学園も申請を行っておりましたが、厚生労働省より職域接種の一時保留の通知がありました。
そのため、今後、本学園で予定しておりました職域接種について、実施時期等が変更となることも予想されます。現時点では、予定通りの日程で準備を進めておりますが、今後、厚生労働省からの連絡により変更となる場合は、7月中旬頃までを目処にご連絡をさせていただく予定です。
つきましては、現時点で本学での接種を希望されている方につきましては、そのような状況をご理解いただき、他の接種会場での接種も含めて、各自でご判断をいただきますようよろしくお願いいたします。
【本件のお問い合わせ先】
学校法人光華女子学園
新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム
[E-mail] vaccine@mail.koka.ac.jp
新型コロナウイルスワクチン予防に係る職域接種の実施について
2021.06.22
本学園は、新型コロナウイルスワクチン職域接種の開始に係る政府の発表を受けて、新型コロナウイルス感染拡大防止に係る社会的要請に応え、地域自治体におけるワクチン接種の負担軽減等に貢献するとともに、本学園の学生・生徒・児童・園児・教職員等、学園関係者の健康と安全・安心を守り、学校生活を安心して送れるようにするため、学生・生徒(18歳以上)および教職員等を対象とし、ワクチン接種を実施することを決定いたしました。
【実施概要】
◆時期:2021年7月~8月
◆対象:大学生、短期大学生、大学院生、高校生、学園教職員等のうち、 18歳以上で接種を希望する者
◆規模:2,000人以内
◆ワクチン:政府配付の「モデルナ社製ワクチン」
※本事業は、ワクチン接種を強制するものでは決してありません。接種しないことにより、不利益を受けることはありません。
【本件のお問い合わせ先】
学校法人光華女子学園
新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム
[E-mail] vaccine@mail.koka.ac.jp
ニューノーマル時代に生きる
2021.06.21
新型コロナ感染症のパンデミックをきっかけに世界は大きく変わることになりました。そしてコロナ禍からポストコロナ時代に向けて社会全体が進み、これからの「ニューノーマル(新しい常識)の時代」に生きるということについて、しっかりと考える必要があります。ニューノーマルとは、社会に大きな変化が起こり、変化が起こる以前とは同じ姿に戻ることができず、新たな常識が定着することを指します。実は「ニューノーマル」という言葉は今出現した言葉ではありません。2000年代初頭、ネット社会が到来したことにより、これまでのビジネスモデルや経済論理が通用しなくなった後にも、またリーマンショックの金融危機の後、資本主義社会から持続可能な社会への変革が起こった時にも、このことが論じられています。
今回の新型コロナ感染症拡大後のニューノーマルは、感染リスク低減のため、人と人との接触を減らす、人と人との距離をとるなどの感染予防を前提とした社会活動・経済活動・新しい生活様式への移行となります。
ここで、日本で馴染みの深い有名な句、平家物語(琵琶法師語り手)の語り出しの句を紹介いたします。
「祇園精舍の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。奢れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もつひにはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。」この意味は、平家の時代が終了して世の中が変わったことから、この世は常に変わりゆく、「諸行無常」と、どんな人も必ず衰(おとろ)えるという「盛者必衰」を仏教的価値観において表現していますが、実はこれだけを意味しているものではありません。「この世の全てのものは絶え間なく「変化」し続けている」ということも伝えているのです。つまり、人生や命、繁栄が「無常」とあれば、この世において生命が誕生すること、発展・成長すること、人々が幸せになることなども、これまた「無常」であるということを言っています。
つまり、ニューノーマル時代への移行というのは、過去にも繰り返されたごく自然なしくみであり、それはいわゆる「無常」の世ではなく、人が幸せになるための変化であることをこの句から教えられます。
その前提において、今回のニューノーマルへの移行については、対人関係への影響が強いため、コミュニケーション不足による対人トラブルや孤独化による心的ストレスがこれまで以上に引き起こされてしまうことが危惧されます。そこで、環境の変化、その影響を受けた我々の人間関係性の変化を、自身の中(心の中)にそれぞれがうまく取り込むことが重要になると考えます。物事に対する受け入れ方や考え方、捉え方によっては、想像していたものとは全く違う景色が現れることを知るべきであり、そうすることで解決する問題も多くあると考えます。一定ではなく、状況は必ず変化する。
この平家物語の句から、無常の世に生きる知恵を授かることができます。
(宗教部)
「光華女子学園奨学会」定期総会中止のお知らせ
2021.05.21
大学院・大学・専攻科・短期大学部の保護者の皆さまに、4月にご案内させていただいておりました令和3年6月9日(水)開催予定の「光華女子学園奨学会」定期総会については、現在の新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、中止とさせていただきます。すでにご出席のお返事をいただいております保護者様には大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、総会の資料につきましては、後日郵送させていただきます。
己を忘れて他を利するは 慈悲の極みなり。 最澄『山家学生式(さんげがくしょうしき)』
2021.05.01
日本仏教の母山と尊称される比叡山延暦寺を訪れると,「忘己利他慈悲之極」の額や言葉が各所で見聞きされます。今月の言葉です。この言葉は,平安時代初期日本天台宗を開かれた伝教大師最澄(七六七~八二二)の言葉です。最澄はそれまでの自己の解脱(迷いの苦しみから解き放たれること)を目的とする仏教から実践的な救済の仏教すなわち,生きとし生けるもの全てが救われていくという仏教・天台宗の実現を目指しました。その学生(僧)養成の制式をあらわした『山家学生式』の中に示された言葉です。
この言葉は,天台宗の僧の在り方を示す言葉であると同時に一人の人間としての在り方を示しているのです。「忘己」=自分のことは後にして,まず「利他」=他者を幸せにする行い,つまり我欲が先に立つような生活ではなく,常に他の人のためにとの心をもっている人を養成したいとの最澄の願いを表した言葉です。その姿は「慈悲の極み」即ち慈とは,慈しみの心であり人の幸せを願う心です。悲とは人々の声にならないようなうめき声を聞き取り,救わずにはおれないという心で,「み仏の心」ということができます。
光華女子学園は「仏教精神に基づく女子教育」を建学の精神に掲げて「清澄にして光り輝くおおらかな女性の育成」を目指して創設されました。そして,校訓を「真実心」と掲げています。「真実心」は如来(仏)のみ心のことをいい,慈悲の心と言いかえることができます。「思いやりの心」「寄り添う心」「他者への配慮」「共に支え合う心」と言うことができるのではないでしょうか。この「慈悲の心」の自らへの実現は,み仏の願いに常に自らを問いかけ自我に偏した生き方を改めていくことです。今月の言葉は光華女子学園の教育の願いでもあるのです。(宗教部)