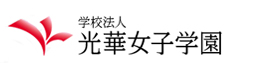法門無尽誓願学(ほうもんむじんせいがんがく) 「四弘誓願」
2004.12.18
仏陀釈尊が開かれた「仏教」。それは一切の苦悩から、我々を解脱(げだつ)に至らしめるための教えであります。自己の去来を明らかにし、自我意識の滅却を果たし、安らかにこの世の終焉(しゅうえん)を迎える心の準備が、仏道であると言えます。それはまた明治の仏教者 清沢満之師(きよざわまんし)が、「生のみが我等にあらず。死もまた我等なり。我等は生死を並有するものなり」と説かれた世界を体感することでもあります。
仏陀の教説には、それを聞く人々の機根に応じて、解脱に至る実に多用な道程が示されています。八万四千に及ぶと言われるその修道過程の中から、自らに相応しい仏道を選び取り、それに専念することで、解脱は果たされるのです。
仏道を歩まんとする者には、様々な法門を学び尽くして、自らが信順できる方途を選び取ってひたすらに生きよとの、仏の誓願が掛けられているのです。(太)
煩悩無数誓願断(ぼんのうむしゅせいがんだん) 「四弘誓願」
2004.11.18
我々一人一人には、無条件に救い取らずにはおかないという、仏の願いが掛けられています。その願いに応えて、我々と共に仏の世界に誘われようとする、理想的人格としての「菩薩」の願いが、「四つの弘い誓願」の名のもとに纏められました。その第二節が「煩悩無数誓願断」です。
いかに心の平静を装うとも、人間である限り、内面には様々な煩悩が頭をもたげます。四苦八苦といわれる煩悩の究極は、生まれたら必ず死ぬという不安であり、食べなければ生きられないという悩みです。この悩みがある限り、人間は聖者にはなれず、凡夫としての一生を過ごすしかありません。
しかしそんな人間にさえ、菩薩の願いは「煩悩を断じさせずにはおかない」という誓願となって、我々一人一人に掛けられています。ある時ふと、「こんなことでよいのだろうか?」と我々が自省の念を持つのは、まさに菩薩の誓願の故なのです。(太)
衆生(しゅじょう)無辺(むへん)誓願度(せいがんど)「四弘誓願」
2004.10.18
仏教が釈迦牟尼仏陀によって明らかにされてから、2,500年の歳月が経ちます。当初は、世の真理を悟るためには、家庭や仕事を捨てて、出家者として厳しい修行に身を置くことが求められました。ところが釈尊が世を去られ数世紀が経つと、繁栄の世の中で仏教に帰依する人々は、仏陀の慈悲を尊びつつ、社会のために働くことの中に、自己の解脱(げだつ)を見ようとするようになりました。老若男女を問わず、あらゆる人々を受け止めようとするこの仏教運動が、「大乗仏教」です。
さらに仏教が真理であるというのなら、たとえ自ら修行のできない人や仏教に背く人々でさえ、救われるはずだとする考えが生まれました。我々一人一人には、無条件に救い取らずにはおかないという、仏の願いが掛けられているとする人間観です。それに応えて、我々と共に仏の世界に誘われようとする、理想的人格としての「菩薩」の願いが、「四つの弘い誓願」の名のもとに纏(まと)められたのです。その第一節が「衆生無辺誓願度」です。
「一人も取りこぼすことなく、衆生を救済すると誓う!」という菩薩の願いにすがることが、大乗仏教の極致なのです。(太)
自我に固執(こしゅう)する見解を打ち破って、
世間を空なりと観ぜよ。中村元訳(『スッタニパータ』1119)
2004.09.18
もともと無(非顕現(ひけんげん))であったところから、否、時間も空間も未だ存在しなかったところから、名(nama)と形(rupa)を通して、今、われわれが見るが如き可視的宇宙は顕現してきた。花には花という形があり、人には人という形がある。しかし、有名・有形なるものはすべて、その可変性と有限性ゆえに、いずれは過ぎ去る虚妄なるものである(同上757)。 さらに、名と形からなるこの現象世界(世間)は、遠くから眺めていると陽炎(かげろう)は存在するように見えるが、近づいてよく見るとどこにも存在しないように、われわれの散漫(さんまん)な心(散心=妄心)には、有りもしないのに有るかの如く見えている空なるものである(非有似有)。それは私(自我)についても言える。ところが、私には私という形(実体)が有るという我執(がしゅう)(見解)に囚われ、われわれは独り生死の世界(世間)を廻っているのだ。そこで釈尊は、自らの教義を「常によく気をつけ、自我に固執する見解を打ち破って、世間を空なりと観ぜよ。そうすれば、死を乗り越えることができるであろう」と纏(まと)めたのだ。 すると、われわれが辿(たど)るべきは、死すべきものから不死なるものへ、形あるもの(有為)から形なきもの(無為)へということになるが、そのためには心(妄心)を除き、世間は空なりと覚るのでなければならない。つまり、河川が大海に流れ込むように、有名・有形の世間に対する妄執を離れ、言葉も及ばず(無名)、形もなく(無形)、かつて一度も時間に触れたことのない非顕現なるもの(法身)と一味になる時、われわれはどこに存在するのでもないが(無我)、至るところに存在する(大我)。かくしてわれわれは、仏教が説く、存在するすべてのものに対して無縁の慈悲を注ぐことができるのだ。(可)
真理は一つであって、
第二のものは存在しない。中村元訳(『スッタニパータ』884)
2004.08.18
仏教が世間と出世間に分けたように、真理にも俗諦(ぞくたい)と真諦(しんたい)の二つがある。俗諦とは世間(この世)におけるくさぐさの真理をいうが、それには社会通念上、真・善・美とされるものから学問が追求している真理も含まれる。一方、真諦とは仏教が説こうとしている究極の真理(出世間の法)であり、それを第一義諦ともいうが、その真理は一つであって、第二のものは存在しないが故に、それを知る時、自ずと人の世における戯言(ざれごと)(争論)は終わりを告げる。
精神(心)と物質(物)、あるいは私(主)と世界(客)はそれぞれ独立した存在であるとするデカルト的二元論から、今日、見るが如く、科学(学問)は急速な進歩を遂げ、そこで問われる真理は、その客観性ゆえに、同じ条件の下では追体験が可能であるというものだ。ところが、この真理の客観性が揺らぎ始める事件が、意外にも、前世紀初頭に活躍した科学者たちの中から起こった。簡単に言えば、科学の探求には観察者である人間の意識(心)も含まれ、観察者である人間と無縁な客観的な世界(物)は存在しないというものである。明らかにこれは、真理の相対性(縁起)を示すものであり、主客(心物)の二元論によって得られる結論はすべて絶対(究極の真理)ではあり得ないということで、仏教がいう俗諦に相当する。
しかし、この心と物が分ち難く結びついているという考えは、早くから仏教(無著(むじゃく)など)の中にあり、また、物(色)を見るとは心を見ることであるから(見色即見心)、心が本来無、あるいは空(無心)であることを体験的に知れば、心(私)だけではなく物(世界)も消えてそこにないだろう。ところが、この見るものと見られるもの(主客)が二つながら無となるところに一なる真理(真諦)を見ていたのが宗教的覚者たちであったのだ。(可)
最上の道を修める人は、
此岸から彼岸に趣くであろう。中村元訳(『ブッダのことば』1130)
2004.07.18
生には二つの旅がある。一つは時間(生死)の中を行くホリゾンタルな旅であり、もう一つは自らの内なる実存(本源)へと向かい、永遠(涅槃)に行き着こうとするヴァーティカルな旅である。源信が「願はくは、われ早 く真性の源を悟りて、すみやかに如来の無上道を証せん」と言ったのは後者である。しかし、われわれは人として生まれ、自らの欲するところに随って人生を演出するが、生死の流れ(此岸)を断って涅槃の岸(彼岸)に趣(おもむ)くことが、われわれの辿(たど)るべき最上の道(無上道)であることを知らない。
ところで、われわれがやって来たところは本源であり(流出)、帰るべきところもまた本源であった(還源)。そこはわれわれが帰るべき永遠の故郷であり、生の源泉なのだ。そして、二つの本源の間(あわい)が生死輪廻する此岸の世界であり、われわれが意識的にヴァーティカルな旅を辿らない限り、生々死々するホリゾンタルな旅はいつ果てるともなく続いて行く。
それは道元の「須(すべか)らく回光(えこう)返照(へんしょう)の退歩を学ぶべし」という警句の中によく表れている。これまで外ばかり向いていた目を自らの内側へと回光(回向)返照して、本源(真性の源)へと立ち返るという意味であるが、学ぶべきは、あるいは修すべきは「退歩」であるとする彼の金言を、今日、われわれは真剣に考えてみる必要があるだろう。というのも、科学技術の進歩にともない、今や人類は宇宙へと飛び立ち、関心は地球圏外へと向けられつつある。しかし、個々の人間にとって、進歩とは未来であり、生き急ぐ時間であり、果ては、死を待つだけのあなた自身は、結局どこに辿り着くこともなく、生々死々する迷道の衆生に留まることになる。宗教とはいつの時代でも進歩ではなく、退歩なのだ。(可)
現世を望まず、来世を望まず、
不死の底に達した人を我はバラモンと呼ぶ。(『ダンマパダ』410)
2004.06.18
仏教は、われわれの陥(おちい)り易い誤ったものの見方に 常見(じょうけん)と断見(だんけん)があるという。前者は、東洋によく見られるもので、人は死んでも魂(私)は不滅であって、永劫回帰などをいう。一方、後者は、人の命はこの世限りのもので、死ねばすべては滅び、死後の世界はもちろん、因果の法則もないというものだ。因みに、もしあなたが虚心に自らを顧(かえり)みれば、自覚の有無はともかく、このどちらかに基づいて人生を歩んでいるはずだ。
最近では、臨死体験者の報告などから、人間は死んでも終わりではないのかと思い、常見に飛び付く人々がいる。しかし、殆(ほとん)どの人は肉体が滅びればすべては終わりという断見に傾いていよう。常見を採る人々は輪廻転生(りんねてんしょう)を言い、死後の世界を説くことが人間の秘密を解き明かすかのように錯覚し、一方、断見は、私利私欲に走る世相がよく表しているように、浅はかな現世至上主義になり易い。しかし釈尊は、どちらの立場もとらないというので、現世を望まず、来世を望まずと言ったのだ。なぜなら、現世と来世、いずれも超えた生と死の彼方にある「不死の境地」を目指しているのが仏教であり、そこに到達した人を彼はバラモンと呼んだのだ。
かく生死を超えることを親鸞は「横超断四流(おうちょうだんしる)」と言ったが、五悪趣(人間も含まれる)の絆を横さまに断ち切って、四生(ししょう)(胎・卵・湿・化)の流れを離れ、彼岸に至るという意味である。本来、仏教に限らず宗教は、常見と断見のいずれでもなく、現世を望まず、来世を望まず、不死の底に達した人であろうとしているのだ。そして、その可能性はあなたが現世・来世のいずれに在ろうとも、常に、あなたの今ここということになる。言い換えれば、生死を離れ、仏と成るのは常に今ここであり、努め励むべきも今ここしかないのだ。(可)
善悪のはからいを捨てて、目覚めている人には、
何も恐れることがない。 中村元訳(『真理のことば』39)
2004.05.18
仏教とは何かを簡潔に纏(まと)めたものに、『ダンマパダ』にも登場してくる、「悪しきことをなさず、善いことを行い、自己の心を浄めること、これが諸仏の教えである」(183)というのがある。釈尊をはじめ、過去の七仏すべてが仏教を上記のように説いてきたというので、古来、「七(しち)仏通誡偈(ぶつつうかいげ)」として知られている。 その彼らが、初めに行為の善し悪しを持ち出してくるのは、仏教が因果の法則を説いていること、つまり、われわれの未来は現在のわれわれが形作るという極めて厳しい倫理観に立っていることに由(よ)る。しかも、ここでいう未来は、ただ死ぬまでの時間ではなく、死をも超えてわれわれの有り様を規定することを含む。例えば、善き業(行為)は順次生(当有)に人・天の受生となるかもしれないが、その縁が尽きれば三悪趣(地獄・餓鬼・畜生)に生まれる恐れもある。それよりも何よりも、人・天といえども六道に輪廻する迷いの存在であって、仏教が説く「安寧の境地」(涅槃)を約束するものではない。それは親鸞が、人・天も加え、われわれが避(さ)けるべき「五悪趣」としたことからも明白である(『尊号真像銘文』)。 翻(ひるがえ)って、善と言えるほどのことを為すことは難しい。否、親鸞も言ったように、悪性はなかなか止められないのが人間という生き物なのだろう。しかし、そんな自分をことさら貶(おとし)めるのではなく、むしろ、善悪のはからいを捨てて、真理に目覚めた人(覚者)となるよう勧めているのが仏教であり、その時、われわれは生死の流れ(六道輪廻)を渡って涅槃の境地(浄土)へと趣(おもむ)く。しかし、そのためには「浄土を得んと欲せば、当にその心を浄むべし」とあるように、心を統一し、自らの心の本性(自性清浄心)を知るのでなければならない。(可)
自己は自分の主であり、帰趨(きすう)である。
故に自分を整えよ。中村元訳(『真理のことば』380)
2004.04.18
齢80になろうとする釈尊が弟子のアーナンダを伴ってある村に滞在していた。45年の永きにおよぶ教化の旅もようやく終りに近づき、その地で彼は最後のとても意義深い説法をすることになる。それは「この世で自らを島(灯明)とし、自らを拠(よ)り所(どころ)として、他人をたよりとせず、法を島(灯明)とし、法を拠り所として、他を拠り所としてはならない」(『大パリニッバーナ経』)というものであった(漢訳で「自灯明・法灯明」と纏(まと)められているもの)。
かつて釈尊は、弟子たちに、自らが生死の流れを無益に経(へ)巡(めぐ)ってきたと語ったことがある。その彼が、入滅を前にして、「自らを拠り所とし(自帰依)、法を拠り所とせよ(法帰依)」と彼らに諭(さと)した意味は何か、われわれは深く味わう必要がある。まず、なぜ彼は、自らを拠り所とせよと言うのだろう。それは、われわれ自身の内側にわれわれが帰趨(きすう)すべき生の源泉、あるいは不動の真理が隠されているからだ。その真理を仏教は法といい、それを知る時、まさに彼がそうであったように、われわれもまた生死の流れを渡って涅槃の世界へと帰って行く。が、そうできなければ、この世とかの世を空(むな)しく往来する迷道の衆生に留まることになるからだ。
すると、自らを拠り所とすることと(自帰依)、法を拠り所とすること(法帰依)は本質的に一つの事柄ということになろう。つまり、真理への鍵はわれわれ自身の自己であり、自分を整え、内なる真実に目覚めることが真理(法)をも知る(覚る)ことになる。かくして、自己の真実に目覚め、真の主となるとき、内も外も、見るもの全てが真実を顕わすが故に、釈尊はヴェーサーリーで、あの矛盾とも取れる、とても印象深い言葉を発したのだ。「この世は美しい、人間の命は甘美なものだ」と。(可)
私は世間におけるいかなる疑惑者をも
解脱させ得ないであろう。 中村元訳(『ブッダのことば』1064)
2004.03.18
釈尊は生死に迷うわれわれ人間を世間(生死の世界)から出世間(涅槃の世界)へと連れ戻そう(解脱させよう)としているのだが、仏と成った彼が、その憐愍(れんびん)の情から、われわれがそうという自覚もないまま、生死輪廻していることを説き、世間から出世間へと渡って行きなさいと、どれだけ勧めようとも、それを信ぜず、敢えて仏法を蔑(ないがし)ろにする不遜の輩を解脱させることはできないと言う。
それは、一遍の言葉に「三毒(貪・瞋・痴)を食として、三悪道の苦患(くげん)を受くること、自業自得の道理なり。しかあれば、自ら一念発起せずよりほかには、三世諸仏の慈悲も済(すく)うことあたわざるものなり」とあるように、われわれが生死の苦海を転々としているのは、われわれ自身が招いた結果であって、誰がそれを強いたわけでもない、まさに自業自得なのだ。また、そうであるからこそ、一念発起し、自ら「不死の境地」を求め、悟りの世界(涅槃の世界)へと赴(おもむ)こうとしない限り、たとえ仏であっても如何(いかん)ともし難い、と彼が言うに同じだ。
仏教が、われわれ迷道の衆生に対して慈悲の心を注ぎ、解脱(生死出離)に向かわせようとしていることはまぎれもない事実であるが、この度(ど)し難い人間(疑惑者)の耳に彼らの声は届くこともなければ、まして、たまたま人間として生まれたこの機会を捉えて、生死の流れを渡るのでなければ、「いずれの生においてか、この身を度せん」と言った覚者(道元)の気遣いなど分かるはずもない。ともあれ、生死輪廻の輪を廻しているのは他ならぬわれわれ自身であり、止めるのもまたわれわれ自身であることを銘記しておこう。(可)