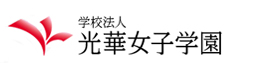心が統一されたならば、
豊かな智慧が生じる。 中村元訳(『ブッダのことば』282)
2004.02.18
心を整えることによって生じてくる智慧があると釈尊は言う。それは、道に世間道と出世間道の二つがあるように(親鸞『教行信証』)、知にも二つあるのだ。まず、主客の関係で知識を積み上げていく世間知、例えば、学問の場合、研究する者がいて、研究対象として自然や社会がある。そこから得られた新たな知識やデータを集めて一つの理論(論考)を纏(まと)め上げる。この構造が世間知であり、学問というのも世間知の範疇(はんちゅう)を超えるものではない。それに対して、主客の認識構造を断じたところが出世間智であり(それを「真智」という)、仏教が説こうとしているのはもちろん後者である。というのも、仏教はわれわれを世間(生死輪廻する世界)から出世間(涅槃(ねはん)の世界)へ連れ戻そうとしているのであり、そのための智慧を出世間智といい、それは誰もが本より具えているというのが、釈尊の悟りであったのだ。
では、何がわれわれをして出世間智を知る妨げになっているかというと、主客の認識の根底にある心(分別心)なのだ。といっても、それはわれわれが普通に心と呼んでいるものであり、是非・善悪を論じ、富貴を計りながら、徒(いたずら)に混乱し、われわれを永く生死輪廻の絆(きずな)に繋(つな)ぎ止めている心である。そこで釈尊は、この妄(みだ)りに物に移り、物に誑(たぶら)かされる心(妄(もう)心(しん))を統一して、生と死の彼方にある心の本質(真心、本心)を知ることができたら、われわれは生死の軛(くびき)から解放され、豊かな智慧が生じるであろうというのだ。今日、私たちの社会は知識(世間知)に偏重する余り、主客の認識以前の智慧(出世間智)について語られることは殆どない。前者が不要であるというのではなく、それは世渡りの手段であって、仏教は後者を知る時、人は「生死の苦海」(親鸞、慧能)を渡り、涅槃の岸に至るであろうことを説いているのだ。(可)
最後の身体に達した人を
我はバラモンと呼ぶ。中村元訳(『ブッダのことば』400)
2004.01.18
六道輪廻する身体を空海は「六道の苦身」と言ったが、現在、われわれが纏(まと)っている身体もその一つに過ぎないのだ(物質的身体という意味で「色身(しきしん)」ともいう)。そして、死とはそれを脱ぎ捨てることであり、生とは再び纏うことであるが、それに六種(六道)があり、闇路に闇路を踏みそえて、六道に輪廻しているのが衆生(人間も含む)といわれるものである。つまり、われわれは今、たまたま人間という衣装を身に纏って、この地上で夢を追い、世事に明け暮れるが、この保ち難い寿夭(じゅよう)のいのちが「苦身」の一つであることを知らない。
そこで、仏教は、この生死に迷うわれわれが真理に目覚めた覚者(バラモン)となるよう勧めているのであるが、悟るとき、人は具体的にどうなるかというと、生々死々する生存の矢を断ち切って、今生の生が最後の身体となるのだ。親鸞的に言えば、もはや世々生々に迷うことはなく、「滅度(めつど)」(涅槃)に至るということだ。 しかし、それは身体という、いわば物質的な存在の形式(次元)が終わることであって、あなたの存在までもが無に帰することではない。悟るとき、われわれは肉体(色身)の内側にもう一つの身体(真身(しんしん))があると知って(それを「身(色身)の外に身(真身)有り」という)、生死という肉体次元を超え、「これが私の最後の生存であり、もはや再び生を享(う)けることはない」と知るのだ。ところが、われわれは自らの内側に真身(法身(ほっしん))があるとも知らず、それこそ死の瞬間までひたすら身体(肉体)に執着するが、それがために、否、それだけの理由で、再び「血肉の皮」を纏う物質次元へと舞戻り、徒(いたずら)に生々死々を繰り返すことになるのだ。(可)
人間と天界の絆を超え、 すべての絆を離れた人を私はバラモンと呼ぶ。中村元訳(『真理のことば』417)
2003.12.18
自らを省みず人の道を説く大人は多い。私はそれについて異議を挟むつもりは毛頭ない。なぜなら、仏教は人の道など説いていないからだ。仏教とは、文字通り、生死を離れ、仏と成る教えという意味であり、人の道を説くだけならばわざわざ仏教など持ち出すこともない。事実、そんなものを知らなくとも大人は臆面もなく人の道を説いている。しかし、仏教は違う。なぜなら、ともども生死輪廻の陥穽(かんせい)に淪(しず)み、徒に生々死々を繰り返すことになるからだ。
さらに言うなら、仏教は人間であることさえも超えて行こうとしている。親鸞はそれを「人・天に超過せん」(元は『無量寿経』にある)と言ったが、人(人間界)・天(天界)は三悪道(畜生・餓鬼・地獄)に比べれば、善き処には違いないが、それとても六道に輪廻する迷いの存在であることにかわりはない。
天国と地獄、この世とかの世、すべては虚妄の世界(幻影の世界)であり、宗教とはこれらに思いをはせることのように見えるが、そうではなく、宗教が目指す真実はそれらの彼方にある。この世にあっては、できる限り長命と幸せ多きことを願い、死しては天国に生まれることではなく、人間の絆を捨て、天界の絆を超え、すべての絆を離れた人であろうとしているのだ。このように、仏教は本来、人・天すべての繋縛(けばく)を離れた「全(まった)き人」(『スッタニパータ』)を目指しているのであり、それは真理に目覚めた覚者(バラモン)に他ならず、その真理によって幸せであれ!と説いているのが仏教なのだ。この「全き人」を宗教は「まことのひと」(親鸞)、「真人」(禅)、「完全な人間」(キリスト教、スーフィズム)とさまざまに呼ぶ。(可)
止観の法によって彼岸に達したならば、
すべての束縛は消え去る。中村元訳(『真理のことば』384)
2003.11.18
今日、先進国の一員であるわれわれは、かつてないほど自由を享受し、誰もが一度しかない人生を悔いなく、幸せでありたいと願う。が、それだけのために宗教など必要ないし、だからこそ多くの人々は宗教に何の関心も示さないのだ。
それはともかく、宗教、なかでも仏教は、われわれ人間が、今いる此岸(生死輪廻する世界)から彼岸(涅槃の世界)に渡ることを勧め、そこに至る方法(法)を説いているのであり、人として生まれ、悔いなく生きるかどうかではなく、人間の在り方そのものを問い、かつ如何にして生死の縄目から自らを解き放ち、真の自由を獲得するかを問題にしているのだ。つまり自由には、われわれの恣意的な行為が、善悪を問わず、永くわれわれを生死の絆に繋ぎ止めることになる自由(不自由と言うべきか)と、親鸞や空海が言う、真理に適(かな)って、自然に計らわれていく真の自由(彼らはそれを「自然法(じねんほう)爾(に)」、「法(ほう)然(ねん)の有(う)」と呼ぶ)の二つがある。
それでは、何がわれわれをして生死輪廻に繋ぎ止めているのかというと、意外にも、われわれが心と呼んでいるものであり、世々生々に迷いを深めるだけではなく、ややもすればわれわれを三悪道(地獄・餓鬼・畜生)に至らしめる根源に心があることをわれわれは知らない。禅・浄の思想家たちが心を「第一の怨敵」とする理由がここにある。
そして、心は見るもの、聞くもの、何に触れても即座に反応し、われわれは良くも悪くも心に巻き込まれてしまうが、その心を除き、真理に目覚める方法として、古来、仏教が用いてきたのが「止観の法」であったのだ。つまり、心を止めて彼岸に根付き、真理を観照するもう一つの眼(慧眼(けいがん))が開かれる時、すべての束縛は消え去ると。(可)
生と死の両極を見極めないで、
人は徒に嘆き悲しむ。中村元訳(『ブッダのことば』582)
2003.10.18
生まれた者に死を逃れる道はない。生はひたすら死へと向かう走路に過ぎないが、なぜかわれわれは死を遠ざけ、忙しく世事に明け暮れる。しかし、いずれは力尽き、その試み、その夢、その家族・・・すべてを残して、独り死出の旅に赴く時、人は死を畏れ、また愛するものの死を看取り、愁嘆に暮れる。
生まれたと言っては喜びの涙を流し、死んだと言っては悲しみの涙を流す。これが人の世と言われるところであろうが、その実、世々生々に迷っているわれわれ人間(親鸞の言葉)は何度もこの悲喜の涙を流してきた。それ故に釈尊は、生と死の両極を見極めないで、人は徒に嘆き悲しむと言う。まるで、生(生まれる)とは、死とは何かを知った者に悲しみなどないと言わんばかりである。事実、悟りとは、生死の夢(「生もまた夢幻、死もまた夢幻」白隠)から目覚め、生もなければ、死もない永遠のいのち(不生不死の生)に目覚めることであり、かく目覚めたものを覚者(仏)という。つまり、生死に迷うわれわれが死の悲しみから逃れる方法はただ一つしかない。それはこの生死なき本分のいのちに帰っていくことなのだ。
浄土教は本分のいのちを無量寿仏、すなわち阿弥陀仏と呼び、またこのいのちに復帰することを往生という。つまり、われわれがいのちと呼んでいるものは、生じては消える波のようなものであり、それらの根源に繋がる永遠なるいのち(同様に「弥陀の願海」という)に帰入するのでなければならないということだ。でなければ、人は有限の生しか知らず、いつまでも生死の波に翻弄され、徒に嘆き悲しむことになる。(可)
生まれることは尽きた。
清らかな行いはすでに完成した。中村元訳(『スッタニパータ』82)
2003.09.18
チャーンドギア・ウパニシャッドの末尾にわれわれ人間にとって何とも不可解な言葉がある。それは、「あなたは再びこの地上に戻り来ることはない」というものだ。もちろん、死ねばすべては終りだから当然ではないかというような単純な理由から言われたものではない。そして、この言葉は『スッタニパータ』の中にも二度登場してくる。
その一つは、ある村に滞在していた釈尊に対して、バラモンのバーラドヴージャが、種を蒔き耕すことのない者は食べるべきではないと批判したのに対し、釈尊はあなたも自らを耕し、退くことなく努めるならば、二度と渇きを覚えることのない安穏の境地(涅槃の境地)へと赴くであろうと、逆に諭(さと)されたというものだ。それを聞いた彼は、すぐさま田を耕すことを止め、釈尊のもとで出家し、ひとり怠ることなく修行に専念していたが、まもなく次のように覚ったという。「生まれることは尽きた。清らかな行いはすでに完成した。なすべきことをなしおえた。もはや再びこのような生存をうけることはない」。
生まれることが尽きたというのだから、彼(また、われわれ)は今生だけではなく、これまでにも何度か生まれてきたということになるだろう。そして、生(生まれること)あるが故に死が避けられないのであるから、生まれることが尽きるとは、生と死の繰り返しを離れることができたということだ。つまり、釈尊の教え通り自己を開発し(自らを耕し)、安穏の境地に至るものは、もはや生と死からなるこの地上に再び戻り来ることはないということだ。それを親鸞は<滅度>に至ると言ったが、今生でなすべきことをなしおえ、<正定聚(しょうじょうじゅ)>に住する者は、再び生死に迷うことはなく、真実(涅槃)の世界に至るであろうということだ。(可)
世間における一切のものは虚妄である。中村元訳(『ブッダのことば』9)
2003.08.18
世間とは、われわれが今いるこの世界を指しているが、そのすべてが虚妄(陽炎の如く実体を持たないこと)であると釈尊は言う。その一方で彼は、自分にとってここは仏土(浄土)と映っているが、あなた方の目にそうは見えていないということで「我がこの土は浄けれども汝は見ざるなり」(『維摩経』)と弟子たちを前にして言った。しかも、そう見えていないのはあなた方の咎(過ち)にあるとした。しかし、それは彼らだけではなく、われわれにも当てはまる。つまり、われわれが見ているものはことごとく虚妄であるけれども、覚者の目(それを仏眼、あるいは慧眼という)には同じこの世が真実と映っているのだ。
すると、この世が虚妄となるか、真実となるかは認識するわれわれの見る姿勢にかかっていることになろう。果たして仏教は、人間には「世俗の我」と「真実の我」の二つがあるという。もちろん前者は、世間(世俗)に留まって、徒に生まれ、徒に死を繰り返しているわれわれ自身のことであり、後者は真理に目覚めた覚者を指している。つまり、見る私が「世俗の我」であるか「真実の我」であるかによって、世界もまた虚妄ともなれば、真実ともなるのだ。
ところが、ここに重大な問題がある。それは、この世が虚妄であると知るのは覚者に限られるということだ。言い換えれば、「真実の我」(親鸞の言う「まことのひと」であり、臨済の「真人」にあたる)を知るのでない限り、われわれはこの世が虚妄の世界であると気付くこともなく、生々死々を繰り返すことになるからだ。一方、「世間における一切のものは虚妄である」と知った者はこの世とかの世をともに超えた真実の世界に至り、再び空しく生死の円環を巡ることはない。(可)
心の内がよく整えられた者は、
この世とかの世をともに捨てる。中村元訳(『スッタニパータ』7)
2003.07.18
心には妄(みだ)りに湧き起こる妄心(もうしん)(想念)とそれを焼き尽くし、心の内がよく整えられた真心がある。今、われわれは前者を生きているのだが、妄心といってもわれわれが普通に心と呼んでいるものであり、よくも悪くも日夜、思い煩っている心のことだ。そして、「生死はただ心より起こる」(『華厳経』)という命題が正しいとしたら、心ゆえにわれわれはこの世に生まれてきたことになるが、それだけではなく、心の内がよく整えられた者は、この世とかの世をともに捨てるというのだから、心ゆえにかの世(親鸞が「後世」と呼んだ死後の世界のこと)もまた存在することになる。言い換えれば、心ゆえに、われわれはそうという自覚もないまま、この世とかの世を往来し、徒(いたずら)に生々死々を繰り返しているのだ。
一方、この世とかの世をともに捨てた(離れた)ところがわれわれの帰るべき真実の世界なのであるが(浄土の思想家たちが「法性(ほっしょう)の都」と呼んだもの)、もちろんそこは、死ねば誰もが行き着くかの世ではない。もしそうなら、何の問題もなかったであろうし、わざわざ釈尊が、心の内がよく整えられた者と条件など付けはしなかったであろう。事実、心をよく整えて(これが瞑想の意味である)、この世とかの世をともに捨てることは容易でないがゆえに、われわれは無始劫来(むしこうらい)、此処(ここ)に死し、彼処(かしこ)に生まれ、生死際なき輪廻の世界を独り巡っているのだ。
宗教はかの世に神の国や仏国土(浄土)を想定し、死者のみならず、残された者たちの気休めに人類が捏造(ねつぞう)した方便ではない。むしろ、いかなる背後世界に逃げ込むのではなく、この世とかの世をともに離れた真実の世界に復帰することを説いているのだ。(可)
真理に遵(したが)う人々は渡り難い死の領域を超えて、
彼岸に至るであろう。中村元訳(『真理のことば』86)
2003.06.18
死の領域とは、現在われわれがそうという自覚もないまま、生と死を繰り返しているこの世界(此岸(しがん))を指している。それに対して、生死を超えた彼方の世界を彼岸という。そして、仏教(釈尊)は、ここ(此岸)に留まっているべきではなく、われわれが辿る(たど)べきは彼岸であることを指し示し、如何にすれば此岸の世界から彼岸の世界に渡ることができるか、その方法を探ってきたのだ。
しかし、なぜわれわれは今、生死に迷う迷道の衆生となっているのかというと、われわれが真理に暗いこと、すなわち無明(avidya)に閉されているからということになろう。さらに、この無明を根本に貪欲(とんよく)(貪り)と瞋恚(しんに)(怒り)が生じ、これらが相俟って生々死々する無明長夜の闇はいつ果てるともなく続いて行く。翻(ひるがえ)せば、無明の闇を晴らし、真理に遵うならば、死の領域を超えて、彼岸に至るであろうということだ。もちろん、ここでいう真理は諸々の学問が追究しているそれではなく、真智(無著(むちゃく)の言葉)と呼ばれたものであり、それを知る(覚る)ことが難しいが故に此岸から彼岸へと渡ることは容易ならざることなのだ。
浄土教は、死の領域(此岸)を超えて彼岸へと渡ることの難しさを「水火(貪欲と瞋恚を象徴している)二河の比喩」で説明してきた。生死に迷うわれわれの前に東岸(此岸)から西岸(彼岸)へと伸びる一本の狭き白道がある。しかし、それは今、われわれの貪りと怒りの二河に洗われ、容易に渡り難い道であるが、もとよりあなたに代わって渡ってくれる人などなく、あなた自身が意を決して辿らねばならない真理への道(それを仏道という)であると。(可)
覚者の内には勝れた宝が存在する。 この真理によって幸いであれ。中村元訳(『スッタニパータ』224)
2003.05.18
真理に目覚めた者を覚者(仏)というが、彼らは一体何を覚ったのであろうか。それは彼ら自身の内側にある<勝れた宝>を知ったのだ。しかし、それは彼らのみが有していたのではなく、われわれもまたそれを携えている。だから釈尊は、自らの体験を踏まえ、あなたの内側にある宝(真理)を知ることがあなたを真に幸福にするであろうから、この真理によって幸いであれ!と注意を喚起しているのだ。
しかし、われわれはそれあることを知らず、あれもこれも(物、人、金銭、名誉、権力・・・)手に入れようと、求めるのは常に外側(外観)ばかりで、一度たりとも内側を見るということがない。もちろん、そうすることが自分の幸福に繋がると思っているのであろうが、死の時、あなたはそれらすべてを残して、ただ独り去り逝く。空でこの世に入ったあなたは再び空でこの世から出ようとしている。この無知を諌(いさ)めてきたのが仏教に限らず宗教なのだ。
従って、仏法を求めるとは、具体的には、われわれ自身の内に隠された<勝れた宝>を知ることだと言えよう。キリスト教はそれを「大いなる富」と呼び、スーフィズムは「隠れた宝」、禅は「自家の宝蔵」と言ったが、親鸞(浄土教)がそれを「真実の利」と呼んだことは「釈迦、世に出興(しゅっこう)して、道教を光闡(こうせん)して、群萌(ぐんもう)(生死に迷うわれわれ自身のこと)を拯(すく)い、恵むに真実の利をもってせんと欲(おぼ)してなり」(『大経』)と主著に引用している通りである。たまたま人間として生まれ、時間、つまり生と死を超えて、本当にわれわれを利するのはこの真理(勝れた宝)のみであることを銘記しておこう。(可)